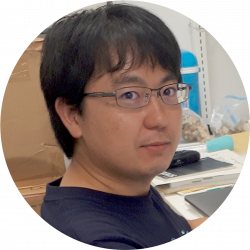恐竜は絶滅してしまった生き物というイメージがありませんか?
実は、恐竜の一部は鳥類へと進化して生き延びており、鳥類は"生きている恐竜"とも呼ばれます。
現在の鳥の特徴を見ていきましょう。2足で歩くのは、人と鳥類だけです。
また、羽毛で空を飛ぶのも鳥類だけ。羽ばたく仕組みはささみと胸肉にありましたね。


そして、抱卵し色とりどりの卵を産むのは鳥類だけです。
内温性(体温を一定に保つために熱を生み出す)特徴を持つのも鳥の大きな特徴です。
2足で歩く、羽毛で飛ぶ、抱卵する、熱を生み出す。
この4つの特徴をすべてもつ鳥類は、いかにして出現し、絶滅をのりこえ、現在の多様な姿かたちへと変わっていったのでしょうか。
現在の姿からだけではわからない鳥の進化の歴史は、動物の化石を調べることであきらかにすることができます。
中生代から現代まで続く、恐竜たちの進化の道のりをご紹介するのが今日のセミナーでした。
今回のセミナーは、対象を小学生にまで広げて実施しました。
難しい内容もありましたが、多くの皆様に受講いただくことができました。

◎参加のみなさまの感想など
・わかりやすく、楽しく聞くことができました。時間があっという間でした。
・恐竜は絶滅したのに、鳥類が生き延びてきたのは、歯を失ってくちばしを発達させたことに関係あるとは思わなかった。
・11000種という数の多さ、鳥類の多様化にびっくりした。
◎田中主任研究員より

鳥は我々ヒトの生活に欠かせない生き物です。
おいしい卵かけご飯も、鳥がいないと食べられません。
ヒトが誕生したのは700万年前、鳥類が誕生したのは1億5000万年前です。
そのうえ、鳥類の特徴の多くは約2億3000万年前から徐々に進化してきたものです。
この偉大なる「地球の先輩」に敬意を払いつつ、今夜も焼き鳥を楽しみましょう!
(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)