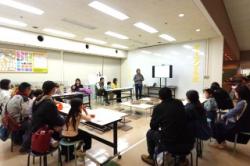福崎町のカッパのガジローは、日本の民俗学の第一人者である同町出身の柳田國男の著書『故郷七十年』に出てくる駒ヶ岩の河童(ガタロ)がモチーフです。
その福崎町からお越しいただいたボランティア連絡協議会のみなさまに「神と妖怪の地域づくり」のセミナーを受講いただきました。
佐渡島の加茂湖に伝わる妖怪「一目入道」の説明がありました。
そのお話がフィクションかノンフィクションにかかわりません。
地域の人々の生活で語り継がれ、伝統行事として残っているものがあるのです。
これまで普段何気なく過ごしている空間も、そこにあるものや地域に伝わるおはなしを知ることで、目の前の風景の見え方が変わりますね。

自然災害の多かった日本では、災害を誘発する要因や、予兆・前兆、被害の回避、災害の履歴など「妖怪」をとおして語り継がれてきたのです。
また、少子高齢化が進み地域コミュニティーが希薄になってきた地域の神社を中心として、新たな地域づくり、健康、防災へとつなげる取り組み例の紹介がありました。
参加された方々が、まちを歩きながら、お互いに地域資源を共有する。
大きく妄想を膨らませ、地域の価値を見出し、可能性を広げていく。
日本のあらゆるところにその種はありますね。
◎参加されたみなさまの感想など
・先生のお話を楽しく聞かせていただきました。
・地元福崎町のことがよくわかりました。
・ぜひ福崎町で子どもたち向けに、講演会やワークショップなどをぜひ行ってほしいと思いました。
よろしくお願いします。
◎髙田主任研究員より

妖怪のまちづくりで有名な福崎町のみなさんとお話できてうれしかったです。
ぜひ、妖怪あんぜんワークショップを福崎で開催しましょう!
(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)