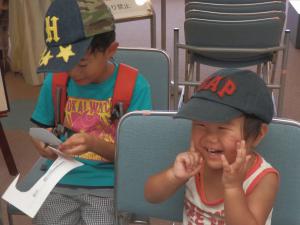ひとはくの周りの深田公園では、
今日はツクツクボウシとミンミンゼミが元気に大合唱していました。
夏休みが終わって、幼稚園、学校が始まりましたね。
キッズの皆さん、元気にしていますか?
秋の訪れを感じさせる、少し高くなった青空のもと開催された
9月のKidsサンデーでのキッズの皆さんの様子をお伝えします!
<自然ってすごい~バッタ☆ラボ~>
昆虫はかせのお話を聞いて、本物のバッタがどれだけ はねるか実験しました。
「バッタとキリギリスは どこがちがうか、わかるかな?」


<ダンゴムシをさわろう>
いろんなダンゴムシのなかまや小さな生きものにさわりました。


<ふしぎなバランスとんぼづくり>
真剣に制作中&にこにこ笑顔で応援中!「がんばって~」

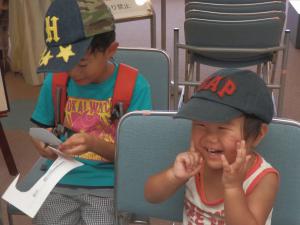
<パネルシアター>
NPO法人人と自然の会の皆さんが楽しいお話をしてくれました。
「ふしぎ!お月さまが光ってる!」


<自然ってすごい~ぴょんぴょん☆プレイルーム~>
本物のバッタやカエルを見たり、はねる生きものの工作をして遊びました。


この他にも館内のあちらこちらで開催されたプログラムに参加して、
ひとはくを楽しんでいるキッズの皆さんを見かけましたよ。


次回のKidsサンデーは10月5日(日)です。
だんだんと外で過ごしやすい季節になってきました。
お天気なら、お昼ごはんは 深田公園でピクニックもいいかもしれませんね!
(たかせゆうこ/キッズひとはく推進プロジェクト)