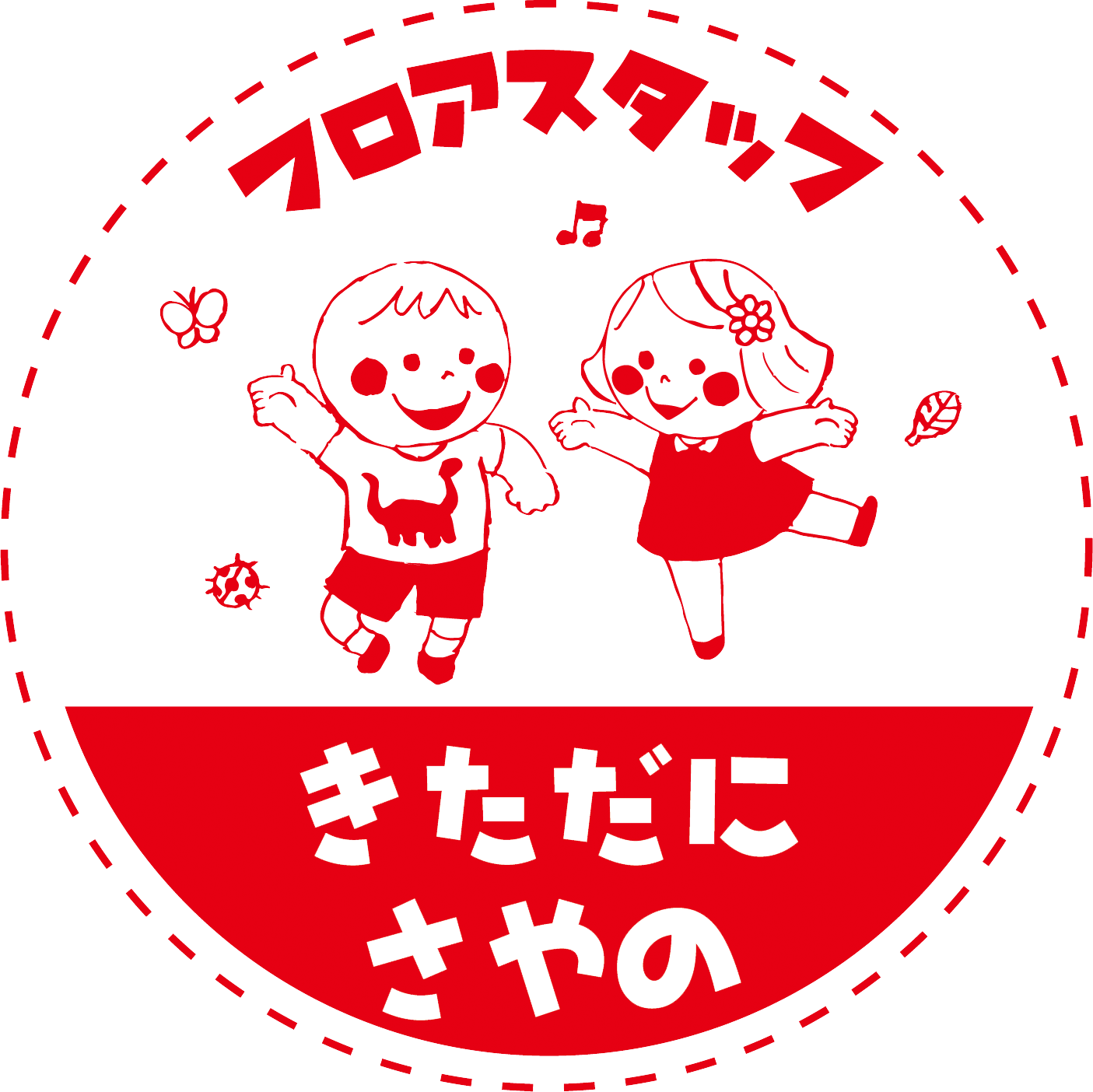少し早いけど・・・☆・*∴。☆★メリークリスマス!★☆.∵.。!(^^)!☆・*∴¨☆∵¨*.・。*.・∴。*.
12月5日(土)に行われたフロアスタッフとあそぼう!「クリスマスリースをつくろう!」にご参加くださいましてありがとうございました。年内まだまだたくさんのイベントを準備しております。またのご参加を心よりお待ちしております。(*^_^*)♪ (フロアスタッフ てらおゆみこ)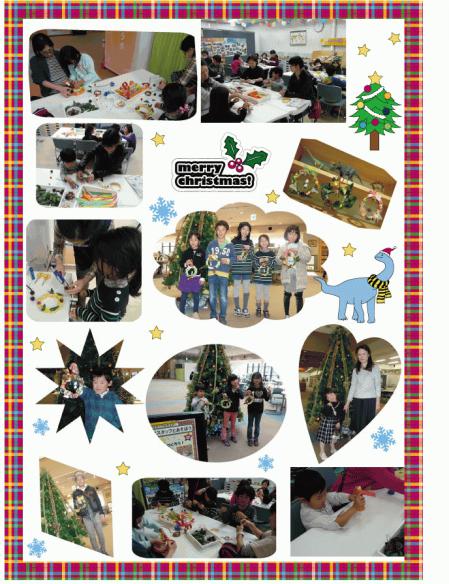
少し早いけど・・・☆・*∴。☆★メリークリスマス!★☆.∵.。!(^^)!☆・*∴¨☆∵¨*.・。*.・∴。*.
12月5日(土)に行われたフロアスタッフとあそぼう!「クリスマスリースをつくろう!」にご参加くださいましてありがとうございました。年内まだまだたくさんのイベントを準備しております。またのご参加を心よりお待ちしております。(*^_^*)♪ (フロアスタッフ てらおゆみこ)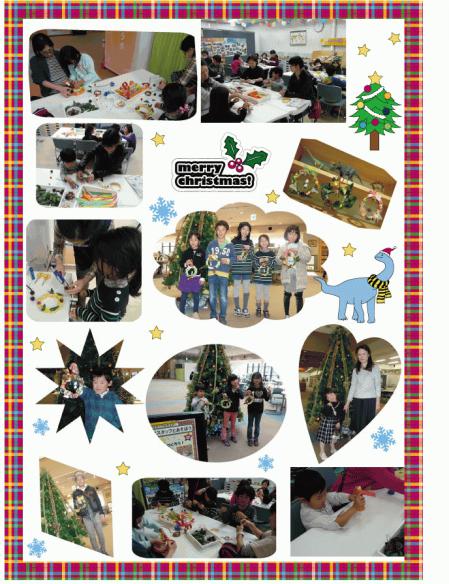
12月2日に「ゆめはく」は、淡路島に行ってまいりました。
今回は今年度限りで閉校が決まっている淡路市の北西部にある淡路市立富島小学校(淡路市富島)を訪問しました。
全校児童数は50名で来年度から近隣の室津小学校とともに北淡小学校に統合されるとのことです。
児童のみなさんに思い出と感動を「ゆめはく」は届けます!
淡路に向けて出発! 明石海峡大橋を渡るゆめはく 

淡路市立富島小学校到着です。 展示の準備中です。 

昆虫タペストリー いろいろなひっつきむし 

ティラノサウルス頭骨 淡路の化石

「丹波竜の話」 「淡路の化石の話」 

「木の実の話」 ドングリの説明

オオスズメバチが大人気でした! ティラノサウルスの大きさにびっくり!

富島保育園のみなさんも見学 チョウチョがきれいですね!

ゆめはくも満員です! チョウチョとガの違いは何かな?

化石や植物のお話の中で子どもたちは熱心に手をあげたり、質問をしてくれました。
なかにはかなり専門的な質問もあり、子どもたちの勉強熱心さに感動しました。
帰るときはグラウンドから子どもたちが大きく手をふってくれて、とてもうれしかったです!
スタッフ 高橋 晃・半田久美子・坂田昌隆・塚本健司・中前純一(記)
小さな学校キャラバン2015はこちら
ひとはくにクリスマスがやってきました![]()

4階ひとはくサロンにて、恒例の クリスマスイルミネーション が設置されています。
ツリーと一緒に記念撮影もできますよ。
▲左が昼間の様子です。夕方になって館内が薄暗くなるとイルミネーションが映えますね。
今年は、華やかなゴールドのツリーもあります+.。゚

← 「クリスマス★メッセージボード」 コーナー
クリスマスかざりに自由にメッセージをかいて
ツリーにかざりつけしませんか?すきな絵をかいてもOK♪
ご希望のお客さまは、
4階のスタッフに気軽にお声掛けくださいね![]()
12月も クリスマス★スノードームづくりなど色んなイベントをご用意しております。
▲くわしくは、こちらをクリック
ひとはくは12/27(日)まで開館しております。
年末年始のおやすみ 2015年12/28(月)~2016年1/2(土)
フロアスタッフ まつだ
もうクリスマスまで1カ月をきりました。
クリスマス一色の町にとてもうきうき(^^)♪
さて、今回はクリスマスにぴったり!
「マツボックリでツリーをつくろう!」のイベントを行いました!
可愛くデコレーションして、自分だけのオリジナルツリーをつくりましょう★
まずはマツボックリのお話から。

マツボックリの種はどんな形?
みんな興味深々!
お話の後は早速作業開始です!
ビーズにお星様に、雪の結晶...どれをつけようかな?

もう完成間近!うきうきするね!
仕上げはお父さん、お母さんと。
グルーガンでマツボックリを土台につけて完成です(^o^)☆
手作りのツリーとみんなの笑顔。



きっと素敵なクリスマスになりますね!
最後に4階サロンのツリー前ではい、ポーズ♪
可愛いツリーの集合に、スタッフも感激!
たくさんのご参加、ありがとうございました!
次回のフロアスタッフとあそぼうは12月5日土曜日「クリスマスリースをつくろう!」
手作りの可愛いリースをつくってみませんか?
http://www.hitohaku.jp/MusePub/eventdetail/?id=12353
4階サロンもすっかりクリスマス仕様。
ぜひ、綺麗なツリーに会いに来てくださいね。
ご来館を心よりお待ちしております(^^)