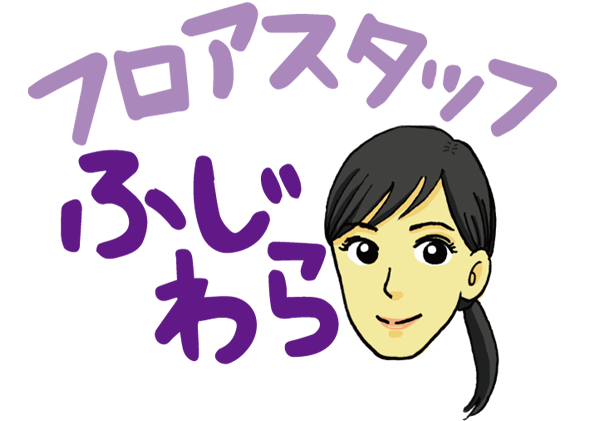月 の 第1日曜日は 「 ひとはくKids(キッズ)サンデー 」です。
12月のKidsサンデー(2日)は、晴れて あたたかく過ごしやすい日でした。
博物館の入口近くのイロハモミジの木は、たくさんの赤く色づいた葉を枝に
付けています。また、ヤツデの木の花が咲いています。
Kidsサンデーのプログラムの様子などの報告で~す。
午前中は、
まずはじめに 研究員による
「サンデーぜみ『赤い葉っぱをさがそう!』」が行われました。
『赤い葉っぱをさがそう!』では、みんなで外にでて赤い葉っぱを
さがして観察したり触ったりしてから採集しました。
その後、部屋に帰ってから、専用シートに貼りつけました。

▲いろんな赤い葉っぱを専用シートに張り付けます
5種類以上の木の、いろんな形の赤い葉っぱがありました!
午前中のフロアスタッフによるプログラムは、
「デジタル紙芝居『ヤマモモの長い旅』」が上演されたり、
「展示解説『3階 ダイジェスト ツアー』」が行われました。
『3階 ダイジェスト ツアー』では、3階の展示コーナーにある
イヌワシやコウノトリなどに関する標本を見たりクイズなどをしていました 。
午後は、
ひとはく連携活動グループの人と自然の会の皆さんによる
「かわいいリースづくり・まつぼっくりのツリーづくり」や
「パネル シアター」が実施されました。
「かわいいリースづくり・まつぼっくりのツリーづくり」では、
いろんな木の実や葉っぱ、いろいろな色や形をした自然素材を使って、
ツルを巻いたものやマツボックリに飾りつけをして作品を作ります。






▲「かわいいリースづくり・マツボックリでツリーづくり」の様子
みなさんステキな作品を作っていましたよ。
「パネル シアター」では、『あわてんぼうのサンタクロース』、
『十二支のはじまり』、『かさ じぞう』のお話を
大きなパネルと貼り絵を使って楽しく上演されていました。
『あわてんぼうのサンタクロース』のお話では、ハーモニカや
スズ、タンバリンなどの音にあわせて、「あわてんぼお~の~♪
さんた くろ~す~♪ ・・・」と みんなで歌っていましたよ。
フロアスタッフによる「デジタル紙芝居『ゆめのつづき』」が上演されたり、
「フロアスタッフとあそぼう!『ひとはくクイズ大会』」が行われました。
『ひとはくクイズ大会』は、チーム対抗でクイズに答えます。
▲『ひとはくクイズ大会』の様子
「フロアスタッフとあそぼう!『ひとはくクイズ大会』」は、
12月1日(土)にも、開催されました。その様子は、
「こんにちは!フロアスタッフです♪ ~ひとはく☆クイズ大会 冬の陣~」
( http://www.hitohaku.jp/blog/2018/12/post_2574/)に報告されています。
午後の研究員によるプログラムは、「落ち葉 de アート」や
「サンデーさーくる『葉っぱ ぐるぐる をつくろう!(秋)』」が行われました。
「落ち葉 de アート」では、いろいろな色や形の落ち葉(押し葉や押し花)などを使って
自由に作品をつくりました。




▲「落ち葉 de アート」の様子
『葉っぱ ぐるぐる を つくろう!』では、用意されていた いろんな色や形をした
葉っぱから、自分で選んで葉っぱをぐるぐる回していましたよ。
葉っぱ~、ぐるぐる回ってますね~。しかも、二人とも 同時に2つの葉っぱを
使っています。
この日、2階で開催中の収蔵資料展「ひょうご五国の自然」に関連する(地学系、植物系、動物系(鳥類)、
まちづくり系の研究員4名が ひょうご五国の自然について リレー形式で解説する)一般セミナーも
開催されました。
そのセミナーが始まる前の時間に、セミナーを実施する部屋の前で、鳥類のはく製を用いての
標本の見方?の解説が行われていましたよ。
▲研究員が鳥類の標本を使って来館した親子に解説しています
また、ひとはくKidsキャラバンで実施している「昆虫キューブ パズル」も登場しましたよ。
▲「昆虫 キューブ パズル」の様子
親子で昆虫キューブ パズルを組み立てています。
<ちょっとした出会事>
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
3階の展示室の丹波竜の展示コーナー近くで、ピコピコ?
(表記がむずかしい?)音がします。
音のする方を見ると、スタンプを押している小さな来館者と
そのお母さんがおられました(近くにお父さんも)。
少し観察をさせてもらっていると、小さな来館者は、歩く
とピコピコ音がなる靴(笛つきシューズ)をはいています。

▲スタンプを押している小さな来館者とお母さん
小さな来館者が押していたスタンプの近くにある
『警鐘』のコーナーに、大きなトラのはく製があります。
それを見つけた、お父さんは、小さな来館者を
抱っこして、トラの顔に近づけて「こわくない?」と
聞いておられました。
▲お父さんに抱っこされてトラを見ている?小さな来館者
小さな来館者は、恐くなさそうでした。というか、
トラには あまり興味が なさそうでした。
お父さんに伺うと、小さな来館者は 生後10カ月
でした。それにしても ピコピコ 鳴らして
しっかり 歩いていました。
また、ご家族で来てくださいね。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
次回の Kidsサンデーは、2019年1月6日(日)に行われます。
ご家族みんなで、ひとはくへ お越しください!
Kidsサンデー プロジェクト 小舘