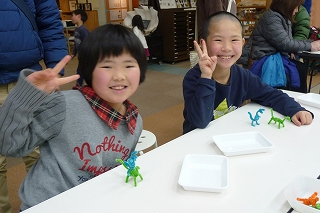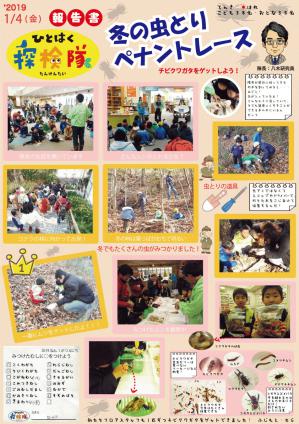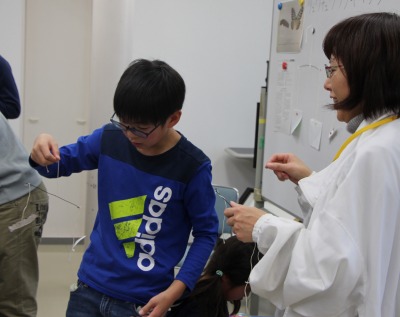月 の 第1日曜日は 「 ひとはくKids(キッズ)サンデー 」です。
1月のKidsサンデー(6日)は、雲が多い一日でした。
博物館のエントランスホール近くにあるエノキの木は、葉っぱも黄色く
なって落ち、たくさんなっていた果実も ヒヨドリなどの鳥類に食べられたのか
ほとんど 枝に残っていない状態です。

▲葉や果実がなくなってしまったエノキの木
Kidsサンデーのプログラムの様子などの報告で~す。
午前中は、
まずはじめに 研究員による
「サンデーぜみ『絵にあう、幹をさがそう!』」が行われました。
『絵にあう、幹をさがそう!』では、みんなで深田公園にでて
動物の体のもようによく似た幹をさがして観察したり、
こすり絵をしたりしました。


▲動物の体のもようににた幹をさがします


▲こすり絵をして 作品をつくります
それぞれ どんな幹を見つけたかな? こすり絵の作品はうまくできたでしょうか?
午前中のフロアスタッフによるプログラムは、
「デジタル紙芝居『ころころ だんちゃん』」が上演されたり、
「展示解説『3階展示室 ダイジェスト ツアー』」が行われました。
『3階展示室 ダイジェスト ツアー』では、(今年の干支の)
イノシシなどの はく製を見たり、台場クヌギ、氷上回廊など
いろいろな展示を クイズなどをしながら まわっていました 。


▲『展示室 ダイジェスト ツアー』の様子
午後は、
フロアスタッフによる「デジタル紙芝居『ヤマモモの長い旅』」が上演されたり、
「フロアスタッフ と あそぼう!『新春!宝さがし ラリー』、
「イヌワシの紙飛行機 を 飛ばそう!」が行われました。
『新春!宝さがしラリー』は、館内の位置図と専用の冊子をもって、お宝をさがします。


▲『宝さがしラリー』の様子
どんなお宝が、見つかった のかな?
「イヌワシの紙飛行機を飛ばそう!」では、いくつかの色の紙が用意されていて、
それぞれ好きな色の紙でイヌワシ型(絵が描いてある)に折って作ります。
できたら、もちろん、 飛ばしま~す。


▲「イヌワシの紙飛行機を飛ばそう!」の様子
お父さんと一緒に 飛ばしている子もいましたよ。
午後の研究員によるプログラムは、「マツボックリでけん玉をつくろう!」や
「チョウのモビールをつくろう!」、「サンデーさーくる『イノシシの
小さなかざりをつくろう!』」が行われました。
「マツボックリでけん玉をつくろう!」では、研究員からマツ類に関する
お話しを聞いたあと、アカマツのマツボックリと紙コップなどを使って
けん玉をつくりました。
つくった けん玉で 上手にあそべるかな? 大人の人も けん玉に夢中になったりして!




▲「マツボックリでけん玉をつくろう!」の様子

▲大人の人も、けん玉に夢中?!!
「チョウのモビールをつくろう!」では、チョウ類の成虫と幼虫の絵に
色えんぴつで色塗りをして モビールにします。


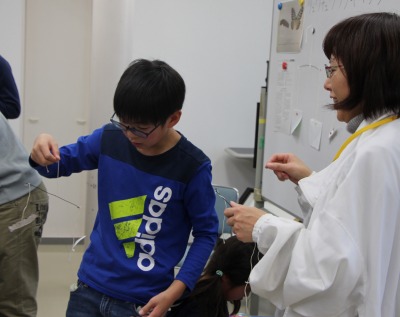
▲「チョウのモビールをつくろう!」の様子
バランスよく、モビールを作れたかな?
モビールをもってハイポーズ!





▲作品と一緒に写真撮影
『イノシシの小さなかざりをつくろう!』では、研究員からイノシシについて
幼獣のはく製や写真を使って説明があったり・・・、
成獣の毛皮などを実際に触ったり、匂ってみたりしました。
それから、ひっつきむしのヒナタ イノコズチ や アレチ ヌスビト ハギなどの
果実の話のあと、ウリボウ(イノシシの幼獣のこと)の形をしたフェルト生地に
目や耳、体のもように みたてて ひっつきむしを貼りつけていきます。
フェルト生地の全面に ひっつきむし を 貼りつけている子もいましたよ。


▲「イノシシの小さなかざりをつくろう!」の様子
作品をもって、ハイポーズ!


▲作品と一緒に写真撮影
それぞれがいろいろで、個性がでますね~。
<ちょっとした出会事>
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
4階の「ひとはくサロン」と呼んでいるところには、
館内のこと を ご案内するフロアスタッフがいる
カウンターがあります。

▲フロアスタッフがいる4階のカウンター周辺
そのカウンター近くで、天井を見てフロアスタッフ
に話かけている小さな来館者(女の子2人)がいました。
どうやら、天井に展示しているダイオウイカの実物大
(体長4m以上)の絵について フロアスタッフに
質問をしているようです。

▲ フロアスタッフとお話している小さな来館者たち
近くにいたお父さんとお母さんに伺うと、2人は姉妹で
小さな来館者は幼稚園児、お姉ちゃんは小学校1年生
で、大阪に住んでいる・・・、 とのこと。
せっかくなので(?)、天井を見ているところの
写真を撮らせてもらいました。

▲天井を見ているところの写真として、ハイポーズ!
お母さんからは、「昨年12月(先月)に来館したけど、
1時間くらいしか 時間がなかったので、年が明けて
あらためて 来ました」とのことでした。
今回は、小さな来館者たちは、姉妹で
いろんなプログラムも体験してくれたようです。
また、ご家族で来てくださいね。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
次回の Kidsサンデーは、2019年3月3日(日)に行われます。

ご家族みんなで、ひとはくへ お越しください!
Kidsサンデープロジェクト 小舘