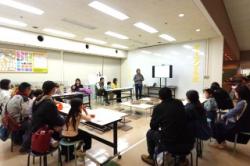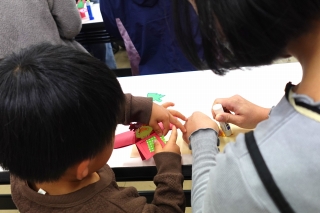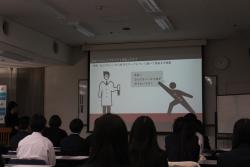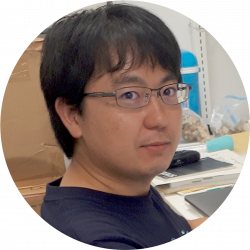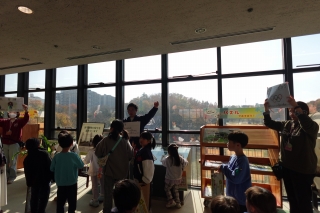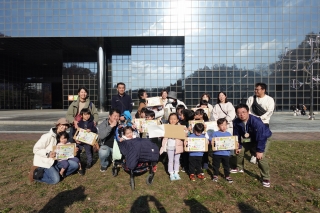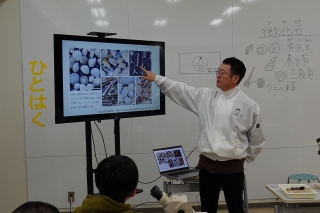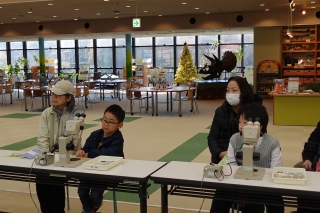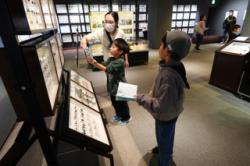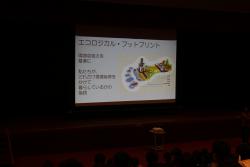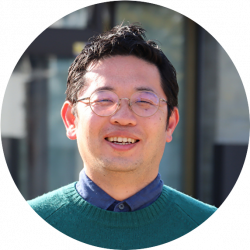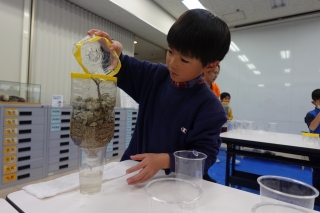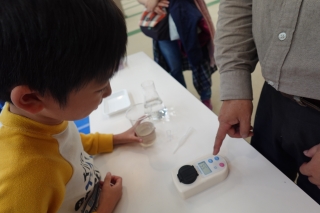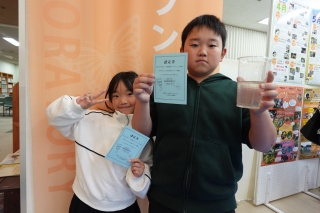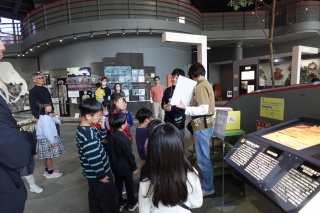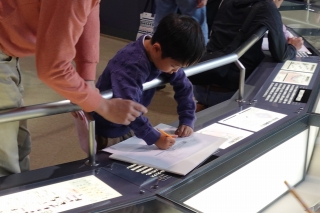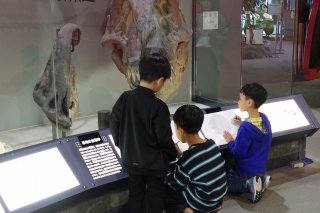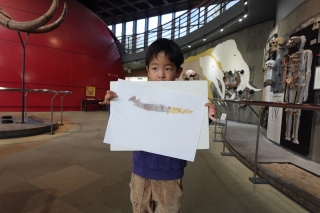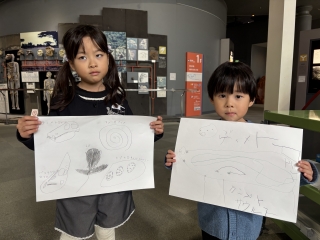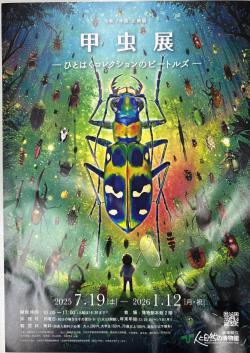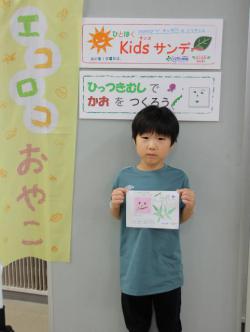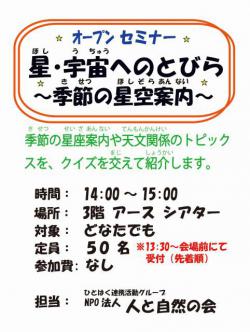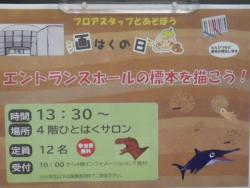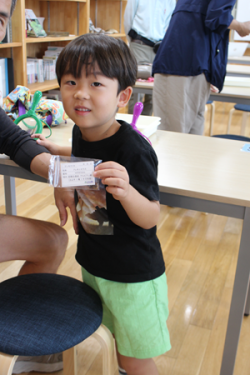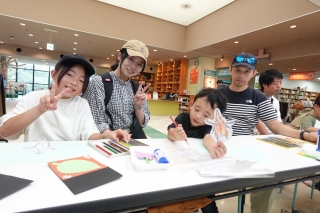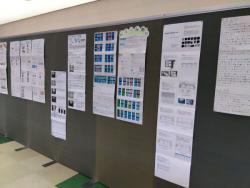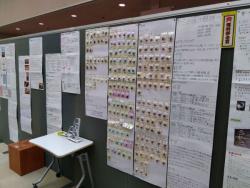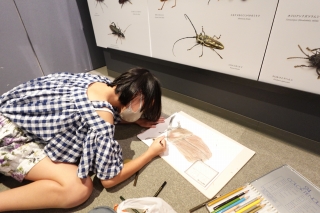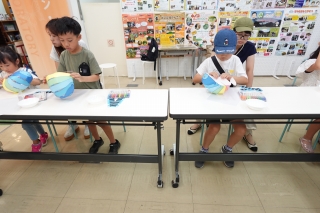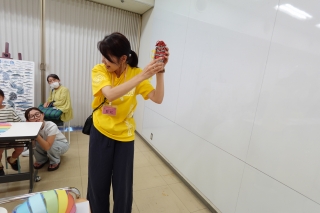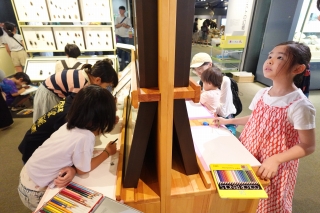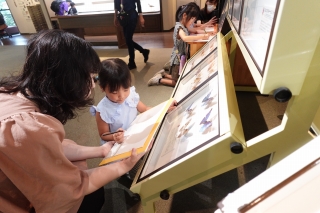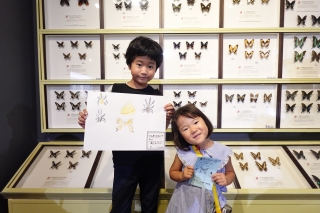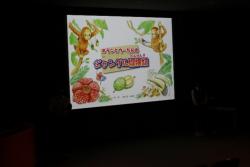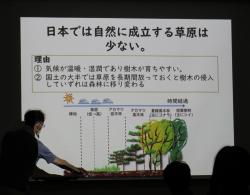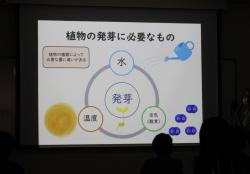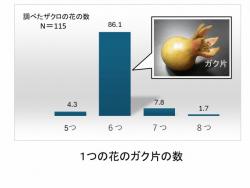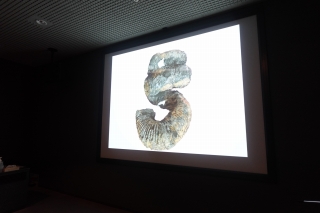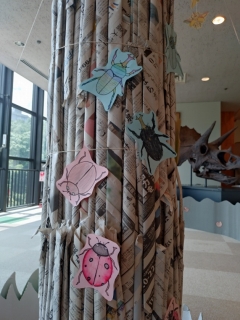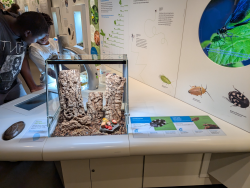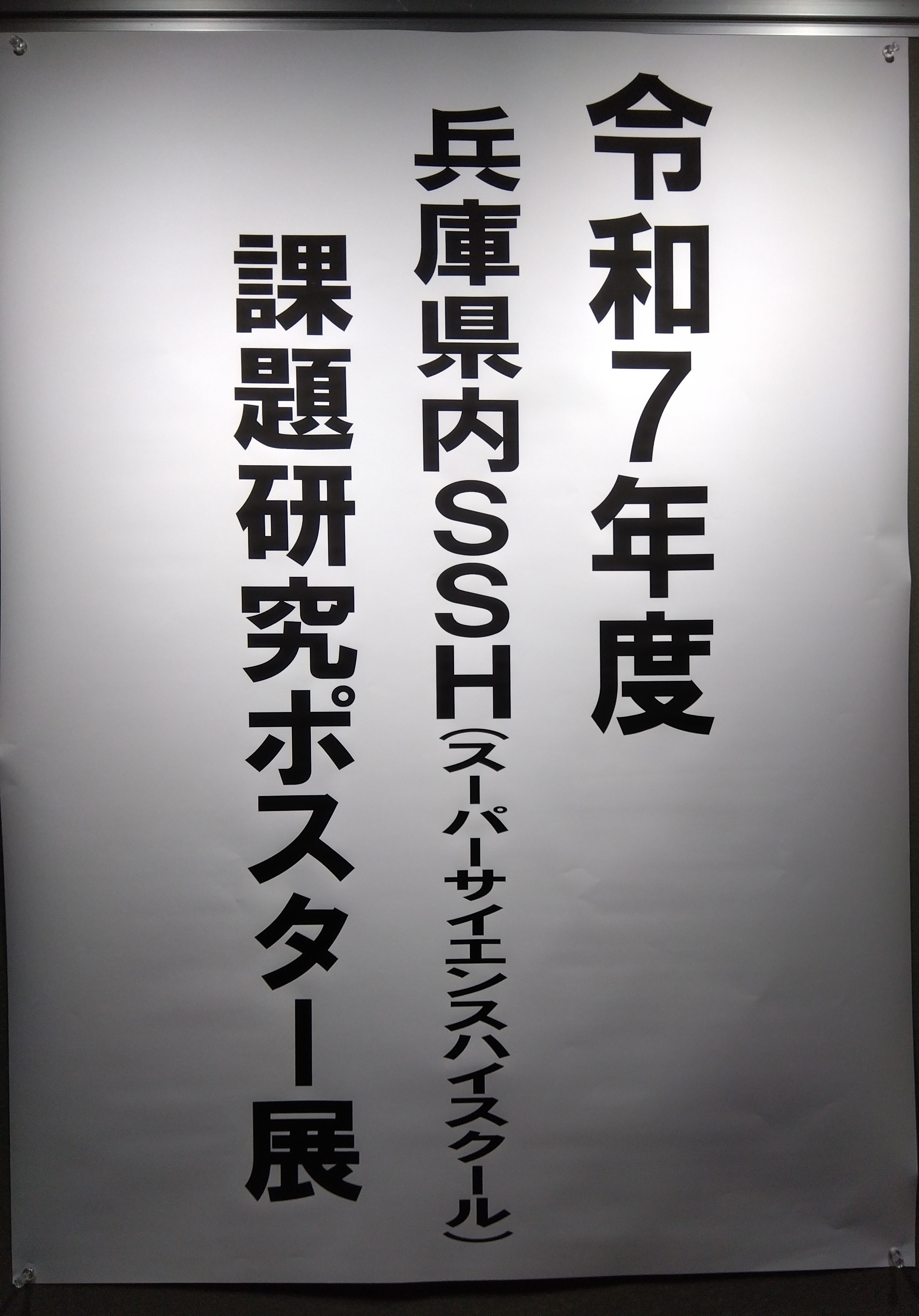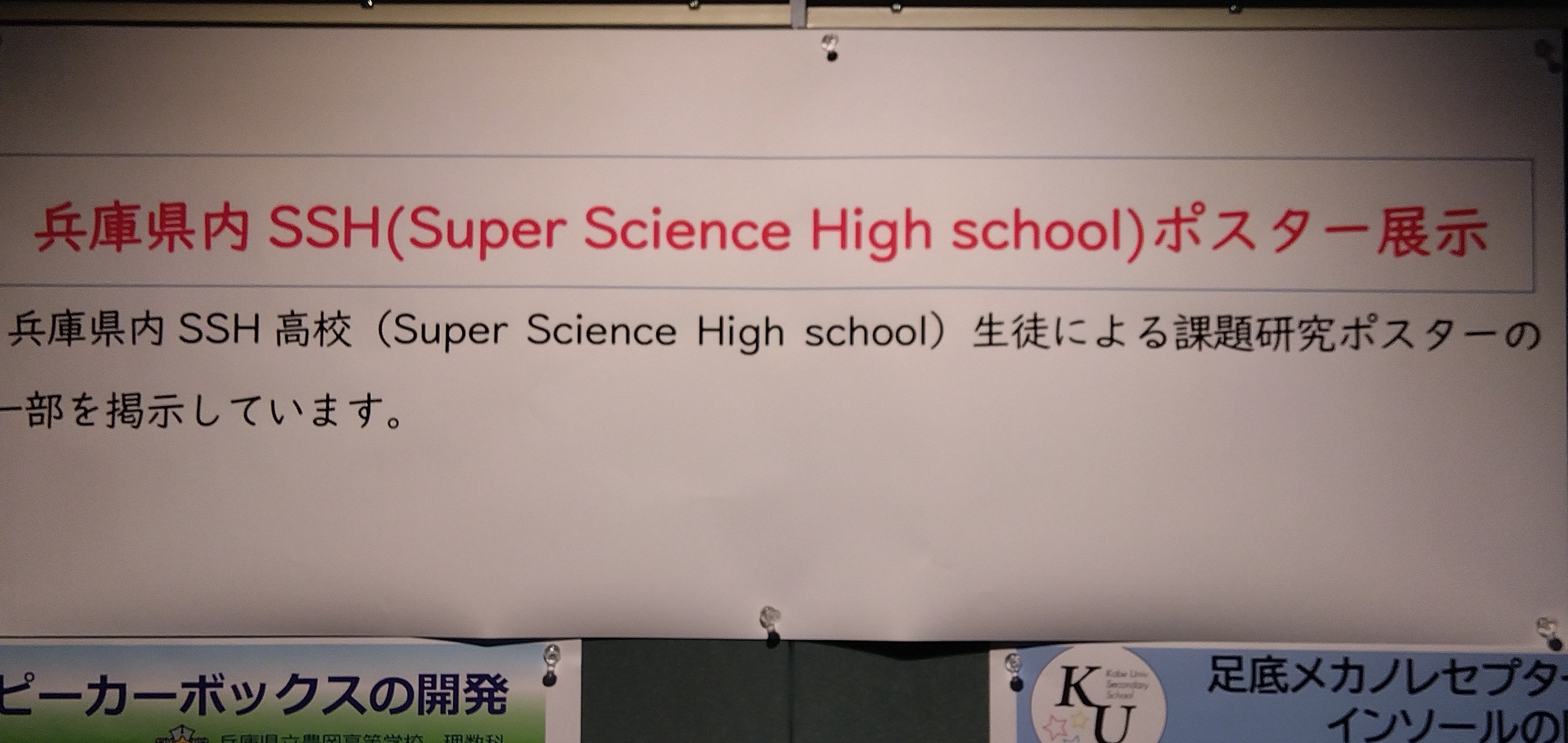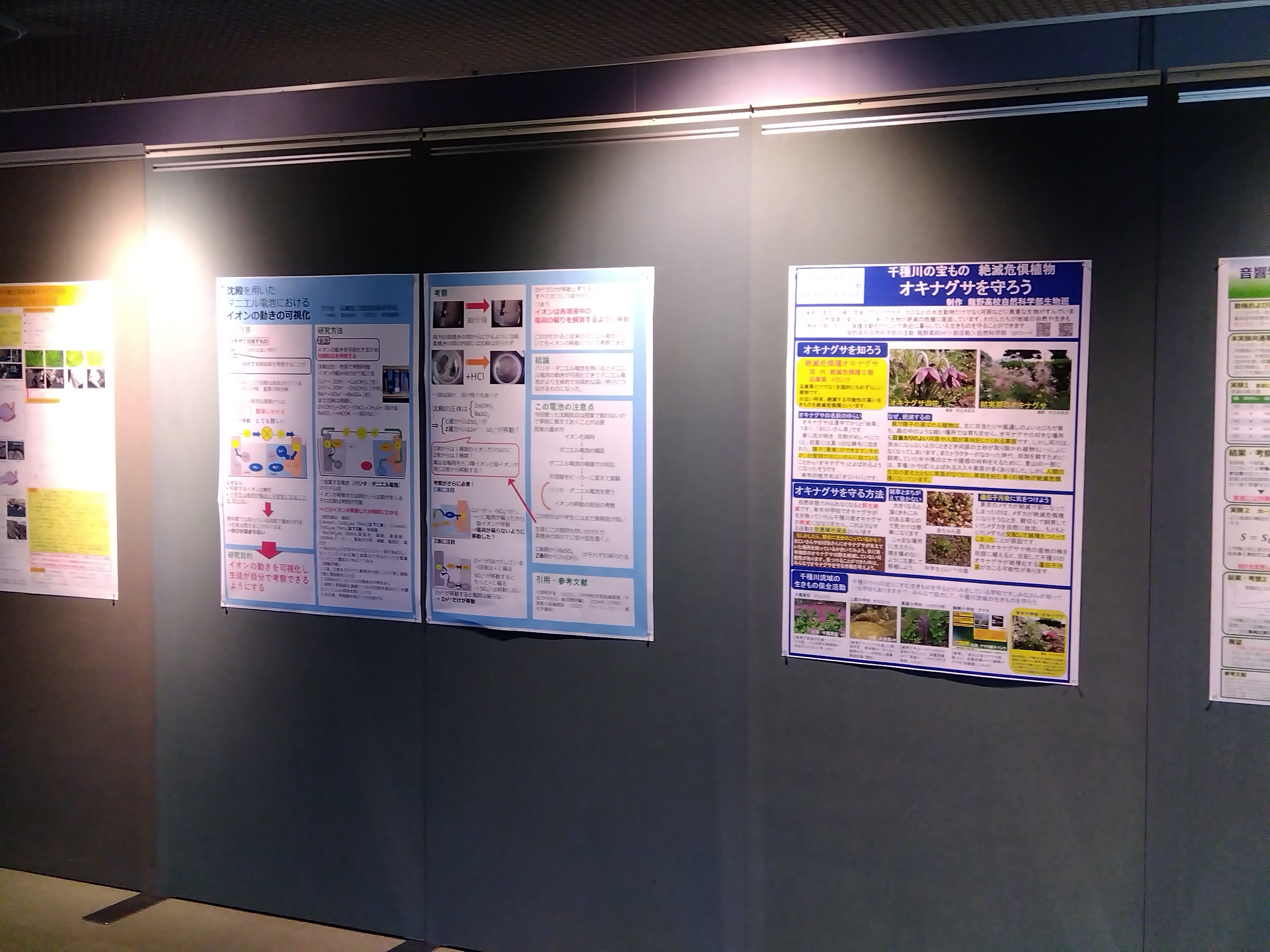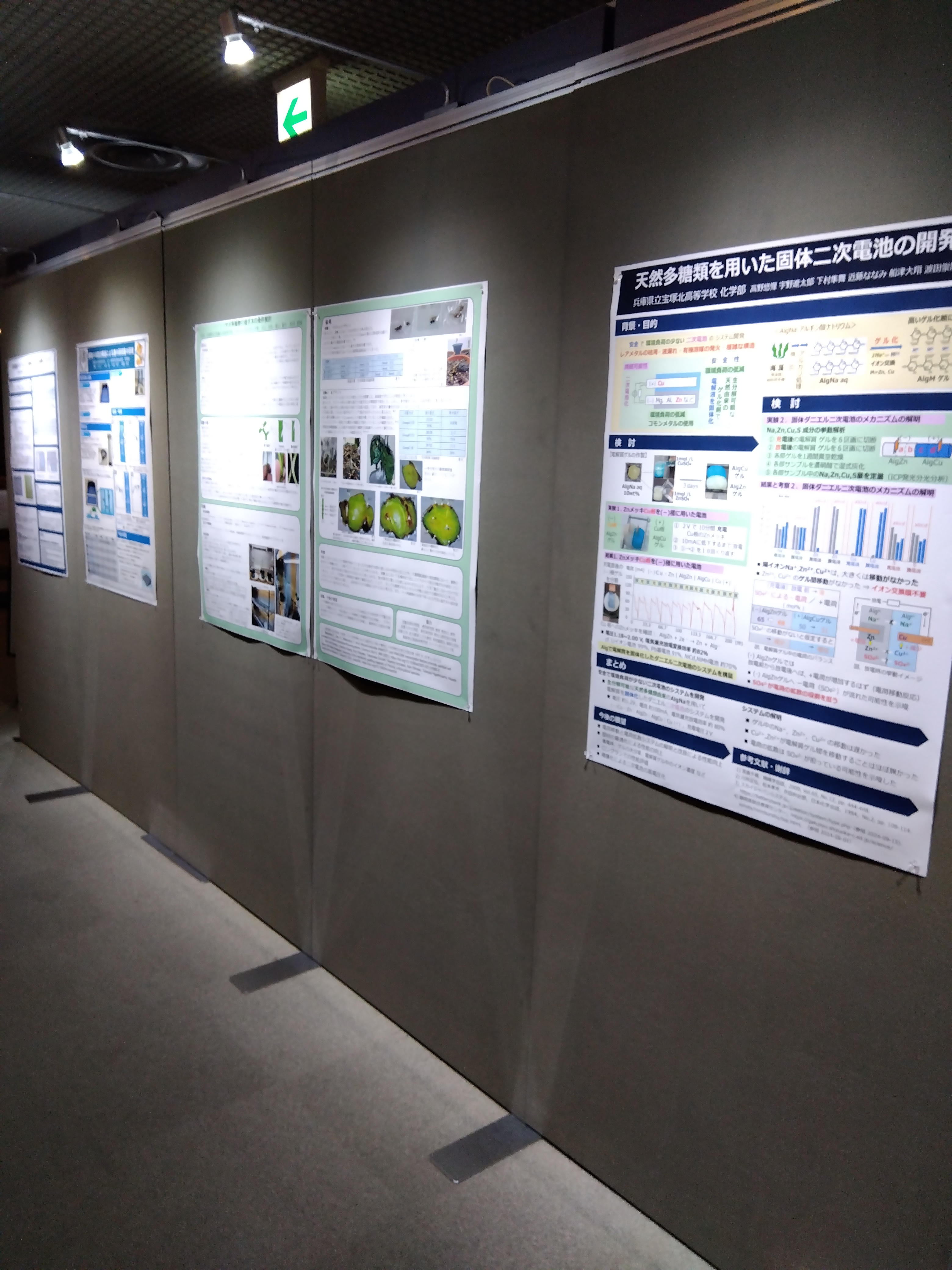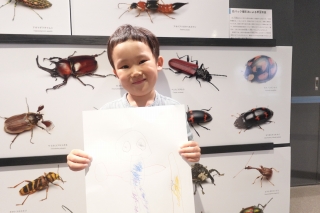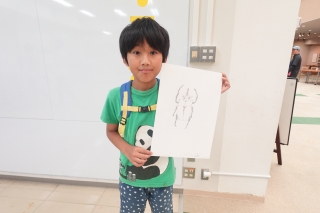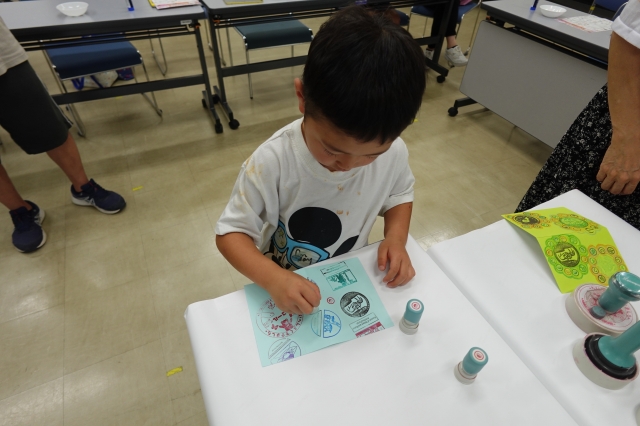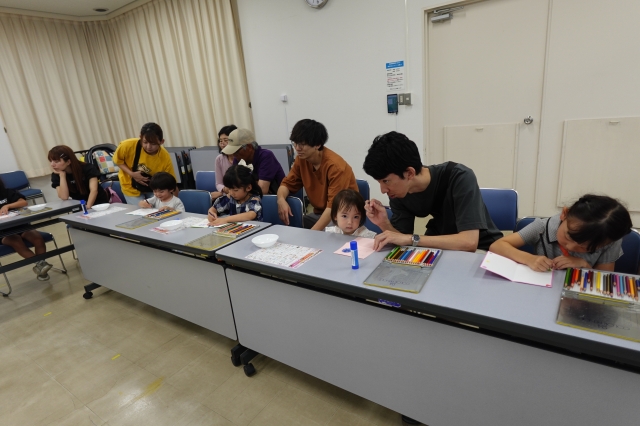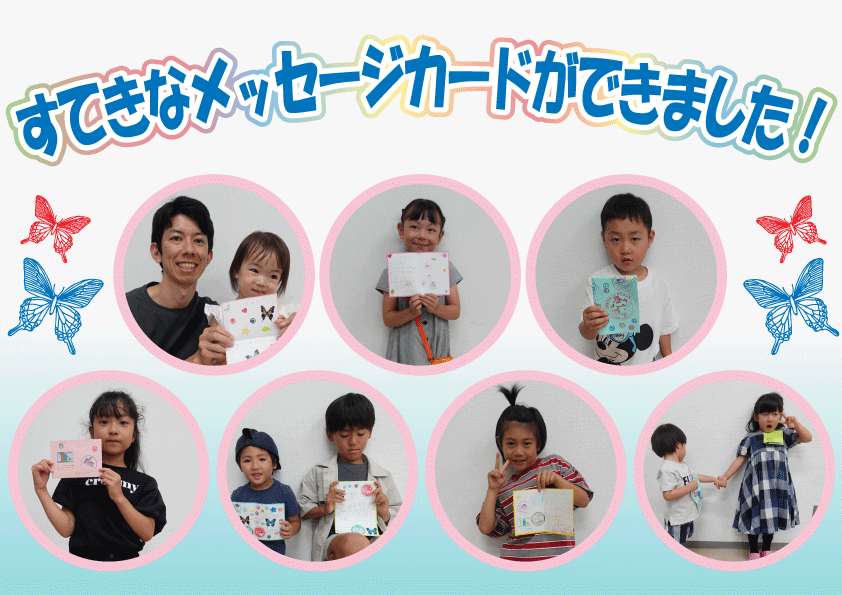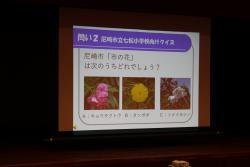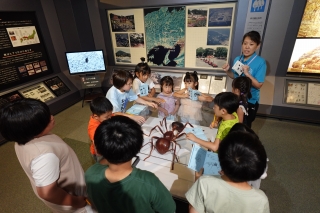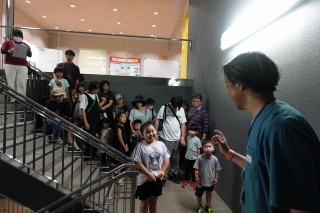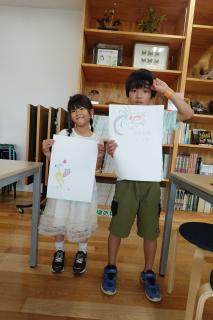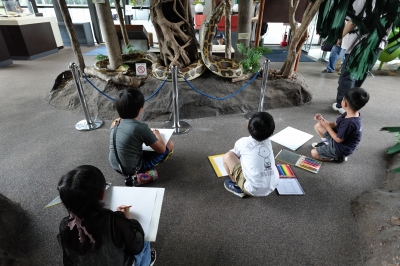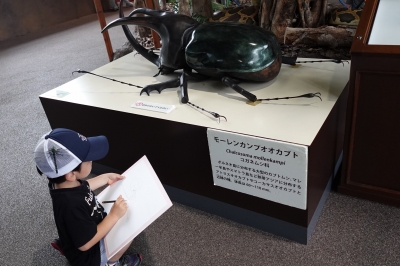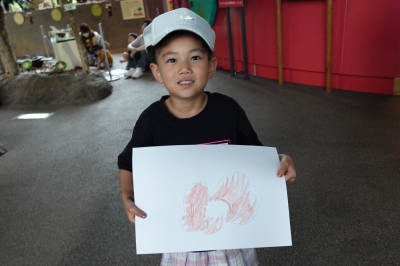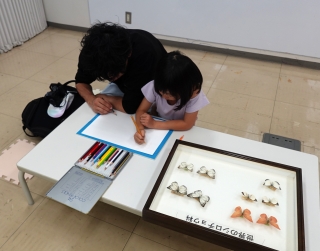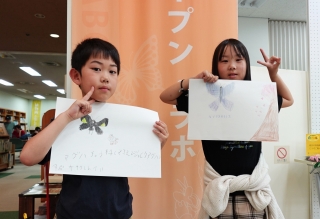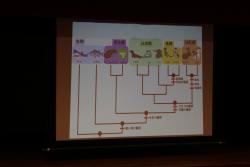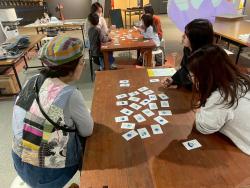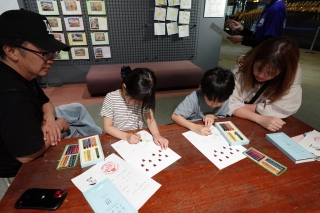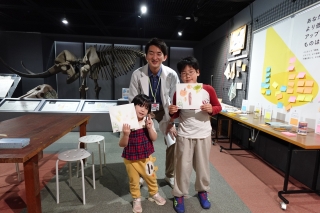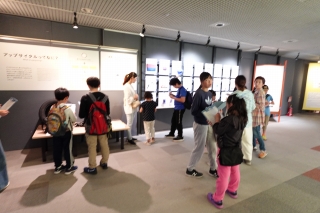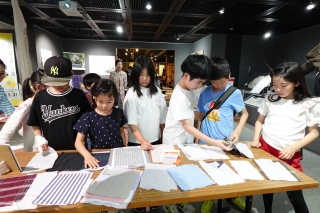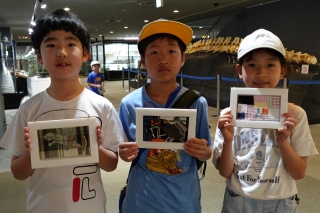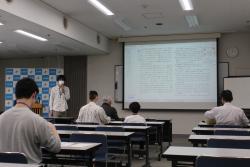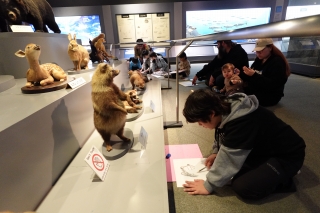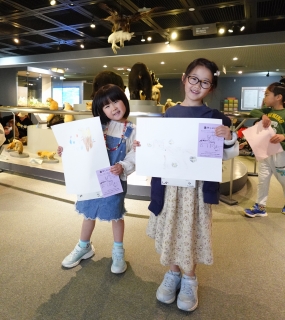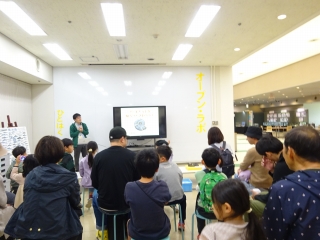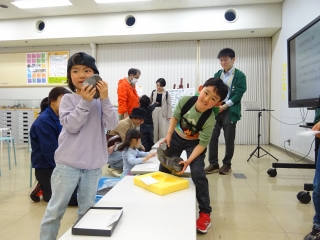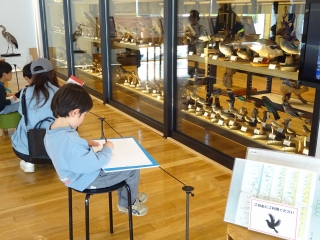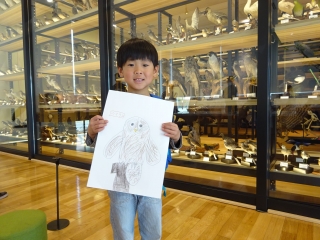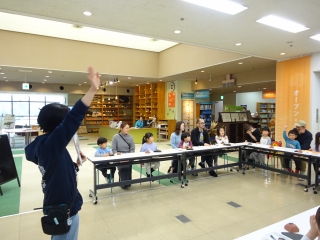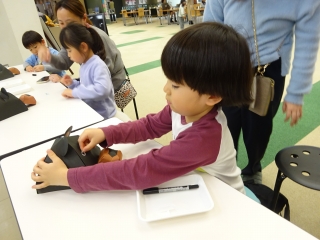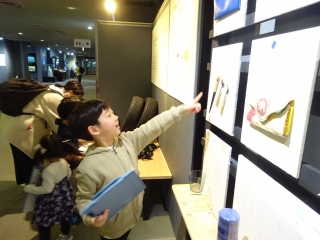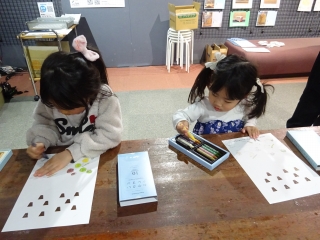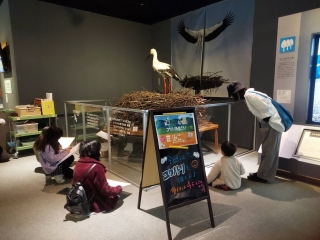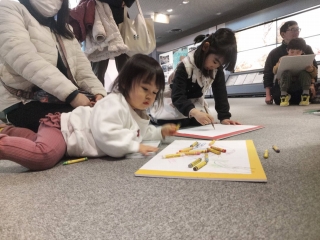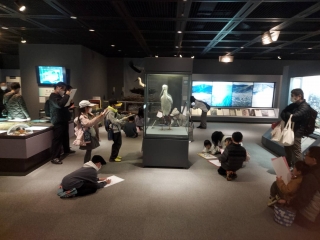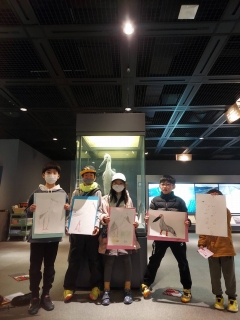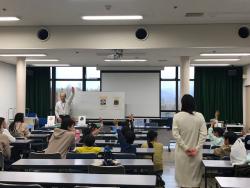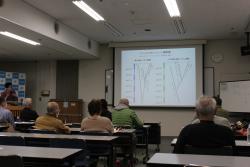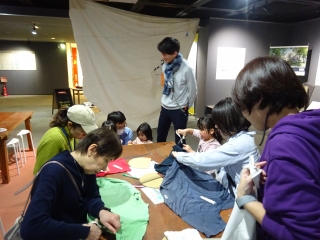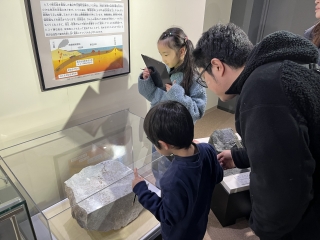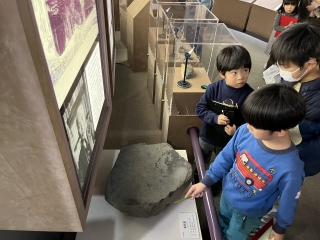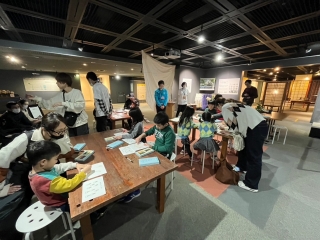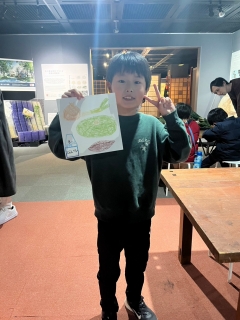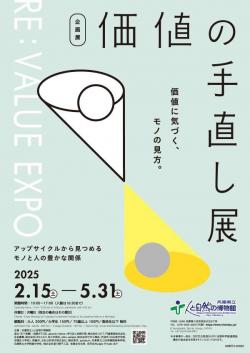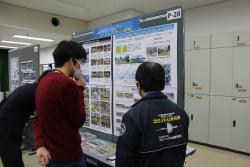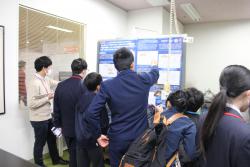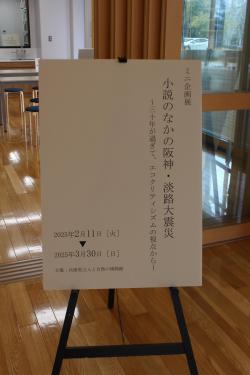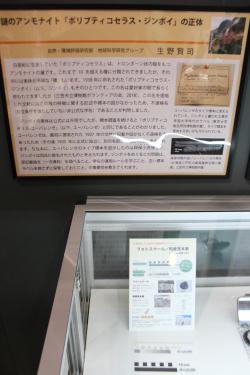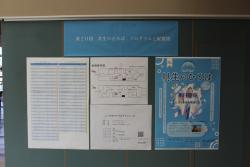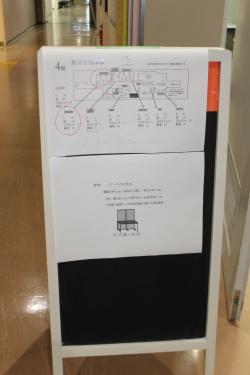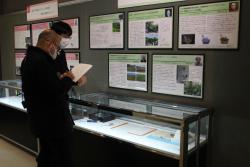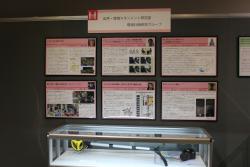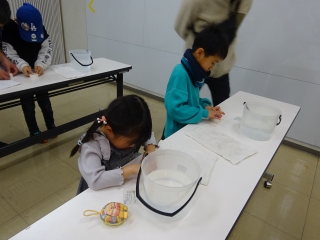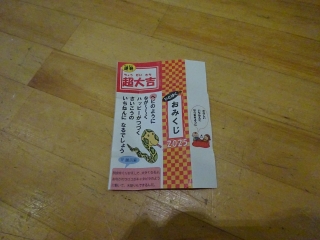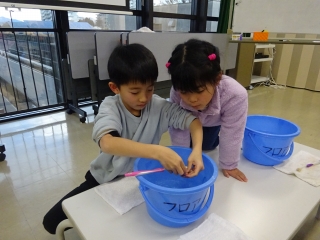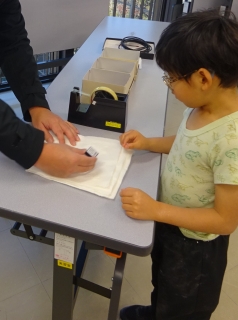色々な植物が植えられていたり、
生えています。
ひとはくの本館横の長い外階段
のちかくにカキノキ(カキノキ科)
があります。
この木には、まだたくさんの果実が
枝に残っています。
※画像をクリックすると、
写真が拡大するものがあります。

▲たくさんの果実がなっている
カキノキ(2025年12月27日撮影)
観察していると、ヒヨドリ
(ヒヨドリ科)が飛んできた
のですが、(私がいたせいか?
それとも)止まった枝からでは
果実が食べにくかったのか、
しばらくキョロキョロあたりを
見回していたのですが、どこかへ
飛んで行ってしまいました。

▲カキノキの枝に止まって
キョロキョロしているヒヨドリ
(2025年12月27日撮影)
外階段上には、清掃の方が掃除を
されたあと、落ちたと思われる
比較的新鮮なカキノキの果実
(部分的なものが多い)が
いくつか落ちていました。

▲外階段上に落ちているカキノキの
果実の一部(2025年12月27日撮影)
お店で売っている柿(カキノキの
果実)のサイズは、たとえば、
小~大まで(直径 約5~10㎝、
高さ 約5~8㎝、重さ 約80~250g)
様々ですが、それらと比べると、
長い外階段の横にあるカキノキの
果実は、かなり小さい果実
(直径約3.5㎝、高さ約3.5cm、
重さ約25g)です。

▲かなり小さいカキノキの果実
(2025年12月27日撮影)
先日、清掃の方が掃除をされる前に
外階段上に落ちていた果実(「かなり小
サイズの果実」と呼びます)
の種子(21ケ)と、
今季私が食べた、お店で売っている
ような果実(「通常の果実サイズ」と
呼びます)の種子(23ケ)の
それぞれのサイズ(長径と短径と
厚み:mm)と重さ(g)を
測定してみました(なお重さは、
それぞれまとめて測定し、
粒数で割ります)。
それぞれの数値は平均して
種子1粒あたりで表示しています。
<カキノキの種子のサイズ(mm)>
=============================
長径 短径 厚み
・かなり小サイズ mm mm mm
の果実の種子(/粒) 16.7 10.5 4.8
・通常サイズ mm mm mm
の果実の種子(/粒) 18.4 13.2 5.6
=============================
<カキノキの種子の重さ(g)>
---------------------------------------
カキノキの果実が 重さ
・かなり小さいサイズ g
の果実の種子(/粒) 0.6
・通常サイズ
の果実の種子(/粒) 0.9
---------------------------------------
それぞれの果実サイズの種子の例は・・・

▲かなり小さい果実サイズの
カキノキの種子の例(左側)と
通常の果実サイズの
カキノキの種子の例(右側)
お店で売っているような「通常サイズ」
の果実の種子に比べると、
長い外階段の横に生えているカキノキの
果実の種子は・・・、
やっぱり、サイズが、ちいさかったタネ~
また 重さが、かるかっタネ~
でした。
よかったら、下記の関連する
ブログ記事をご覧ください。
<関連ブログ記事>
柿食えば、ヒーヨと鳴くなり、果実なくなり?
https://www.hitohaku.jp/blog/2025/12/post_3389/
皆さんも 周辺の環境で生きものの
観察をしてみませんか。
研究員 小舘