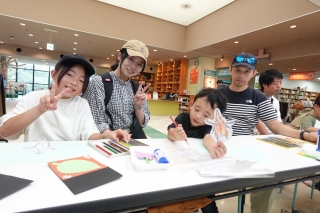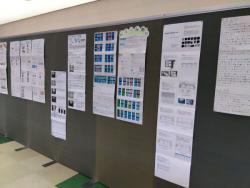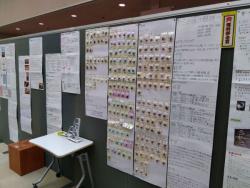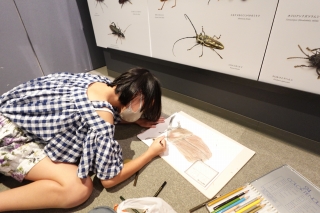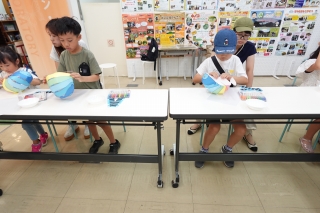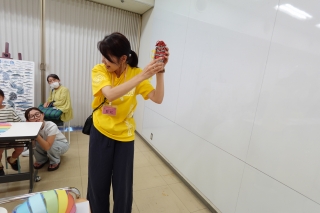色々な植物が植えられています。
エントランスホールの近くに
カエデの仲間 の イタヤカエデ
(ムクロジ科)があります。
※画像をクリックすると、
写真が拡大するものがあります。


▲イタヤカエデの枝葉
(2025年9月下旬撮影)
9月の下旬に、イタヤカエデ
(樹高 約5m、幹の太さが
約14cm)を昼ごろに
観察していると・・・
その木の地上約3.5mの高さの枝
(太さ 約 3㎝)に オオスズメバチ
(スズメバチ科)が複数いるのに
気がつきました。


▲イタヤカエデの枝にいた
オオスズメバチ
何をしているのかと観察していると、
どうやら樹液を吸っているようです。
その日の夕方、小雨が降っていましたが、
同じ枝を確認すると、オオスズメバチが
いました。

▲小雨の中、同じ場所にいた
1匹のオオスズメバチ
次の日の昼に確認してみると、同じ
枝にいました。観察していた範囲では、
最大 7匹 集まっていましたよ。


▲次の日の昼にいたオオスズメバチ
夕方にも再度確認したところ・・・

▲次の日の夕方にもいたオオスズメバチ
喫茶「イタヤカエデ」の枝店
(してん)では、
オオスズメバチによって
(少なくとも2日にわたって、
入れ替わり立ち代わり?で)
貸し切り状態でした。
皆さんも 周辺の環境で生きものの
観察をしてみませんか。
研究員 小舘