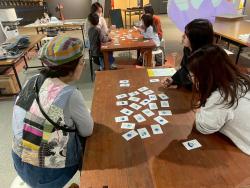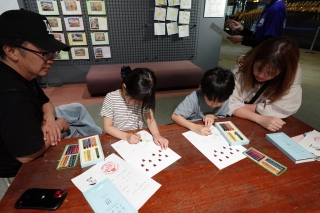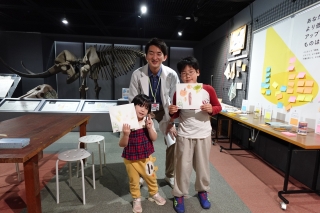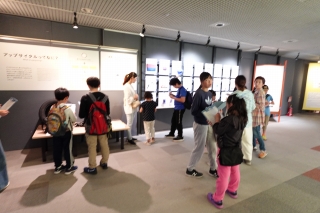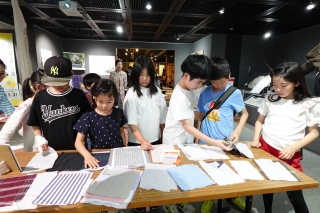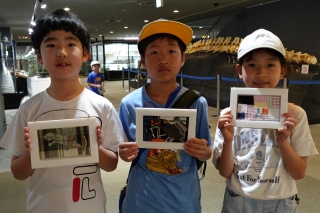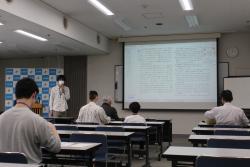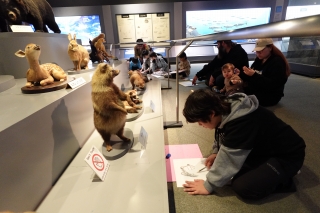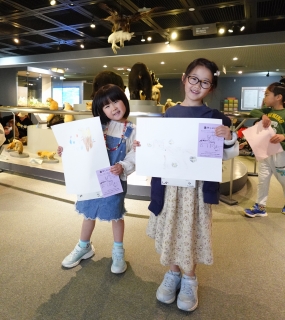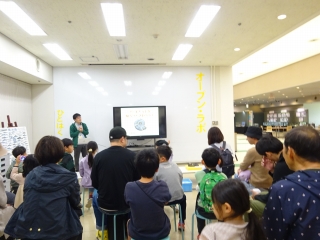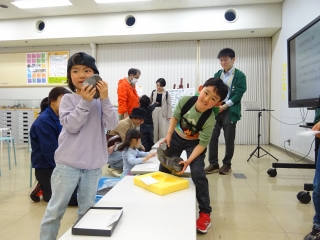今年は飛び石連休ですが、お天気が良い日が多そうです(^-^)
山へ!海へ!大阪・関西万博へ!
おでかけする方も多いのではないでしょうか?
ひとはくサロンではただいま、
ゴールデンウィーク特別企画「古新聞で大きな木をつくろう!」
をおこなっています
古新聞をくるくる巻いて、

葉っぱには色をぬりぬり、


古新聞が大きな木に大変身!
葉っぱもつりさげるよー!
捨ててしまう古新聞がうまれかわったね

こんな風に、いらなくなったものに工夫とアイデアを加えて、ステキな何かを作る「アップサイクル」を紹介する
企画展をおこなっています
「価値の手直し展」~アップサイクルから見つめるモノと人の豊かな関係~←くわしくはタイトルをクリック☆
2025/2/15(土)~5/31(土)
アップサイクルを楽しく学ぶことができます!ぜひ見に来てくださいね!
フロアスタッフのイベントは他にも・・・
3日(土)~5日(月) ワークショップ「とっても簡単!化石のレプリカづくり」
6日(火)ひとはく〇×クイズ大会
そして4日(日)はキッズサンデー!
イベントもりだくさんですよ!
どこに行こうか迷ったら、ひとはくへレッツゴー!(^O^)/
みなさまのお越しをお待ちしております♪
フロアスタッフ一同