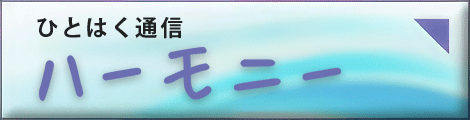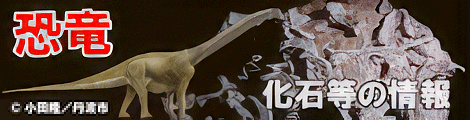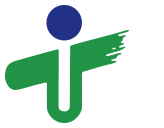ユニバーサル・ミュージアムをめざして44
お隣の山地民
『ゾミア――脱国家の世界史』書評-2
三谷 雅純(みたに まさずみ)
霊長類学や古人類学では、ヒトの進化を百万年単位で考えます。有名なアルディピテクスは、だいたい五百万年前とか四百万年前とかに生まれましたし、教科書でよく見るアウストラロピテクスは、およそ三百万年前に生きていたと言います。わたしたち現生人類(ホモ・サピエンス)にしても、すでに二十万年という歴史を経てきているのです。ですから、スコットさんが『ゾミア:脱国家の世界史』の中で問題にしている千年、二千年という時間感覚は、霊長類学者や古人類学者にとっては「瞬間」にすぎません。山地民の識字率はゼロに近くても、読み書きをする潜在能力があることはもちろんですし、いったん水稲農耕をしていたといっても、もう一度狩猟をする能力は、あるのが当たり前なのです。低地に住んでいた農耕民が、狩猟採集をする山地民になったとしても、何も不思議なことはありません。
わたしたちの思い込みとは、ヒトの社会の歴史は決まった方向に進むと信じていることです。長い長い狩猟採集の時代があって、後に牧畜や焼き畑のような「雑な」農耕の時代を経て、「合理的な産業としての農業」の時代――アジアの例では「灌漑設備の整った水田耕作」――になるのだと思いがちでした。社会ダーウィニズムはそうした考え方をします。ヒトや人の自然への働きかけは、ゆっくりとだが、しかし、確実に効率的になり、まるで単線を走る列車のように決まった終着地に着く。それまで走り続けるというのです。この考え方では、社会が後戻りをすると脱線してしまいます。つまり滅びるのです。カール・マルクスの『資本論』 (1) も、こんな考え方をしていたはずです。
ところが、このわたしたちのこの思い込みは、「国家」という統治機構が創造したのだと言えそうなのです――現代の国家観では、元来、「国家」を統治するのは「国民」ですが、ここでは、あたかも「人格のある人間のように振る舞う国家」が、人びとにある事を信じ込ませたということです。スコットさんはそのことを、「理想と現実の矛盾に気づいた地域の人々や帝国の役人たちは文明論が単なるぺてんにすぎないと見抜いていた」(p 341)と表現します。
ごく大雑把には、霊長類学でも同じような段階は想定しているのですが、それは十万年とか百万年を単位として考えた時の話です。人間が歴史時代になってからの話ではありません。『ゾミア:脱国家の世界史』の中で展開される横暴な政治の支配と支配される人びとの逃避の物語では、まったく時間感覚が違うのです。
☆ ☆
『ゾミア:脱国家の世界史』はディアスポラ(diaspora:国外離散者=風に舞うキク科のタネのようにバラバラになった人びと)やエグザイル(exile:故郷喪失者)の物語です。そして山地民とは、新しい文化を創り出した人びとでした。同じような立場には、ユダヤ人やロマの人びと(昔はジプシーと呼んでいました)、サハラの「ベルベル人」と呼ばれる多くの出自を持った人びとがいます。最近の研究では、南アメリカのヤノマミやトゥピ・グアラニーといった狩猟採集生活で生きる人びとも、インカ帝国や植民地時代のスペインの支配を避けて避難したエグザイルだということです――クロード・レヴィ=ストロースが明らかにしたかった「原始時代から続く人間の『親族構造』や『神話構造』」というものは、どう考えるべきなのでしょう?
ディアスポラやエグザイルと言えば、サハラ以南の熱帯林に住むバンツー諸語を話す人びともそうです。バンツーは森の民ではなく、もともとサバンナに暮らす農民だったのです。それが、今から三千年とか四千年いう時代に地球全体が乾燥化して、サハラに住む人が南下したために、押し出されるようにして森に逃げ込んだ故郷喪失者だと言います。
確かにバンツーの村は、熱帯林のただ中にも関わらず丁寧に草を引き、家の前にゴミなどは落ちていません。これはサバンナに似た雰囲気を作ろうと努力しているのだと聞いたことがあります。
森の奥の村までは、中央政府も統治(支配?)できません。そのため、バンツーの村では、今でも人びとの自治が生きています。この自治のためでしょうか、時には村と村の「戦争」(とバンツーの青年がそう呼んでいました)が起こることがありました。カメルーンのファング(Fang)という集団は、さかんに小さな「戦争」をしたことで有名です。これも大きな「国家」の支配を避ける意味では有効だったのかもしれません。
バンツーとピグミーの交渉には、ゾミアの低地に住む水稲農耕民と山地の狩猟採集民や焼き畑農耕民と似たところがあります。バンツーが畑で取れたキャッサバ芋を提供し、ピグミーはダイカーというウシの仲間の肉や森で集める野菜=グネツムの葉といった物を交換するのです。ただ、ミトコンドリアDNAの分析から、バンツーとピグミーは数万年前には別れていたことが分かっています。その点、ゾミアの歴史とは根本的に異なるのだと思います。それでも、森という見通しの悪い場所は、バンツーに絶好の逃避地を提供しました。バンツーが何か横暴な権力から逃げたというのなら、バンツーはゾミアの山地民と同じ境遇にいたことになります。
☆ ☆
中尾佐助さんの「照葉樹林文化論」は、ゾミアの山地民と同じ地域の文化を基に展開しています。焼き畑農耕、粘り気のある芋やアワ・ヒエといった穀物、陸稲(おかぼ)とかソバとかいった、いういろいろな作物を植え、発酵食品を好む文化は日本にもたらされたといいます。それが西日本の文化の基層になったという仮説です。発酵食品でいえば、例えば琵琶湖のフナ鮨に似たナレズシは中国の貴州省に住んでいるミャオ(Miao)も作りますし、日本の糸引き納豆も、似たものがゾミアを超えてインドネシアにまであります。日本列島とは、言うなら「海に隔てられたゾミア」でした。
日本列島の基層文化とゾミアの山地民の成り立ちとは異なるところがあります。それは水田稲作文化を持ってきたことです。これは佐々木高明さんが書いた『照葉樹林文化とは何か――東アジアの森が生み出した文明』 (2) の195ページに載っていたことです。縄文時代の終わり、弥生時代の始まりの頃でしょう。この時代、水稲農耕の起点とされるようになった長江の下流域では何があったのでしょう? 今の上海あたりの出来事です。
想像するしかありません。思うに「横暴な支配者」に耐えきれなくなった低地の水稲農耕民が領地を逃げ出し、海を越えて、本来のゾミアである山地に代わって九州に渡ってきたということではないでしょうか? 海に漕(こ)ぎ出すことは、山や森に隠れるのと同じ意味があります。「国家」の支配から逃れるためにです。しかも、渡った先にあったのは「未開の島」(=日本列島)です。中国の「帝国の役人たち」も、ここまでは追いかけて来ません。
これが弥生時代の始まりと共に起こったとしたら、「日本」はエグザイル、つまり故郷喪失者が、直接、参加して作られた国だということになります。ただし、そのエグザイルも、水稲農耕という最先端の技術を持っていたために、この日本列島という「ゾミア」に(意に反して?)「国家」を作り出してしまいます。彼らエグザイルは、そのことを望んだのか望まなかったのか、今となっては分かりません。
☆ ☆
ゾミアは日本でも研究が進んだ中世の「アジール」と似ています。「アジール」と呼ばれる場所はゾミアほど広くはありませんが、権力の支配が及ばないところとされています。例えば神社やお寺だそうです。歴史家の網野善彦さんのお書きになった『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』 (3) によれば、犯罪者や離婚をしたい女性ばかりでなく、盲人やハンセン病者もアジールに逃げ込んだと言います。そのような多くの人が逃げ込んだのなら、権力の力が及ぶ一般の市井(しせい)に残った人とは、誰と誰だったのでしょうか?
ヒトの地理分布は、二十万年前までの出アフリカの時代からディアスポラやエグザイルによって広げられました。彼らは地球の寒冷化や飢餓(きが)、病気といった止むに止まれぬ事情があって「ゾミア」に逃げ込んだのでしょう。しかし、それはまた、新天地を開拓する可能性も秘めていました。新天地とは住んで不便なことが多いものですし、思わぬ事件や事故で死んでしまうことも、よくあります。しかし、行かずにただ死を待つより、死んでしまうかもしれないが、それでも行く方がいいと覚悟を決めた出立(しゅったつ)だったのでしょう。わたしやあなたは、そのディアスポラやエグザイルの子どもなのです。
-------------------------------------------
(1) 『資本論 1』(岩波文庫 白 125-1, 882円)マルクス (著), エンゲルス (編さん), 向坂 逸郎 (翻訳)
(2) 『照葉樹林文化とは何か――東アジアの森が生み出した文明』(佐々木高明、中公新書、1,029円)
(3) 『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』(網野善彦、平凡社ライブラリー150、1,223円)
三谷 雅純(みたに まさずみ)
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所
/人と自然の博物館