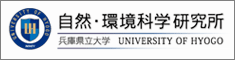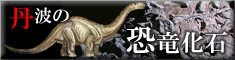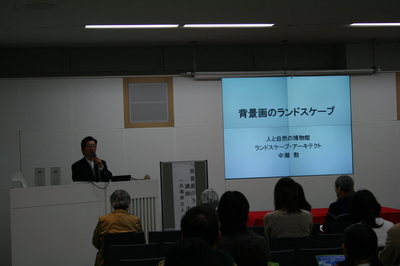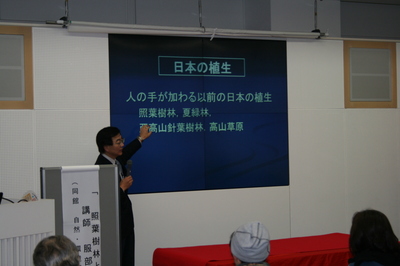中瀬勲副館長の最近のブログ記事
先日、生物多様性協働フォーラムの第3回目が開催されました。
今回のタイトルは、社会の「つながり」を活かした取り組みの展開、です。まさに、多様な主体による参画と協働が意味するところのフォーラムとなりました。会場は、兵庫県庁のすぐ前にある兵庫県公館です。おかげさまで、広い公館が満席となりました。参加者数は450名で、高校生から年輩の方まで、こちらも多様性がゆたか。特に、若い世代の参加が多かったことが印象深いです。
講演では、当館の副館長の中瀬先生からは兵庫県における企業と行政と地域が協働した森林管理の仕組みとその事例について紹介。次に、滋賀県の経済同友会とともに活動されている菊池玲奈さんからは、琵琶湖汽船や滋賀銀行などの企業と連携した取り組みを、同じく滋賀県からブリジストン彦根工場での希少種保全や琵琶湖博物館と連携した取り組みが紹介されました。
フォーラムでは、兵庫県の井戸知事と滋賀県の嘉田知事の対談が、当館の岩槻館長の司会のもと行われました。対談の途中には、会場にいる研究者や環境に優しい農業を推進されている方を指名する一幕もあり、大いに盛り上がりました。90分の対談時間は、ちょっと長いかなと思っていたのですが、あっと言う間でした。会場のアンケートからは、もっと聞きたいとの声が多かったようです。
さらに、この会合には、環境省の渡邉綱男自然環境局長もお越しくださり、しっかりとエールを送って頂きました。多くの環境問題は、関西圏のなかで、府県の枠を超えて対応しなければならない課題が山積
です。しかも、再生すべき場所や保全しないといけない場所はたくさんありますが、予算、人材、人々の関心といった部分でより一層の努力が必要な状況です。こうしたネットワークを活かして、生物多様性をうまく活用し、保全し、再生してゆくことが必要になるのでしょう。このときに、博物館がハブとして大きな役割を果たせればと思います。



兵庫県公館のロビーでは各団体や博物館のブースが設営されました。
左上:大阪市立自然史博物館、右上:琵琶湖博物館、左下:ひとはく、右下:三重県立博物館
となります。どこの博物館もそれぞれの個性がでています。
琵琶湖博物館さんは、今回のフォーラムで移動博物館「どこでも琵琶湖博物館」のセットの一部を初披露くださりました。型どりした湖産の魚や象の歯など、ハンズオングッズが充実しています。滋賀県内だけでなく、関西圏全体で、いろんな博物館が協力して、「どこでも博物館」になることを期待したいと思います。非常に充実した会合でした。
(みつはしひろむね)
ひとはく謎の講談師、河南堂珍元斎でございます。
あけましておめでとうございます。本年もよろしうご贔屓のほど・・・。
さて、県美ひとはく連携事業の一席でございます。
時は、昨年の12月13日(日)。
それは、県立美術館で現在開催中の特別展「ジブリの絵職人男鹿和雄展」にあわせ、背景美術作品の中に登場するさまざまな自然、いきもの、人の暮らしなどを科学的にひとはくの博士が解説する「ひとはく背景画セミナー」で、この日は「〜里山とランドスケープ〜」と題した1回目でございます。
「となりのトトロ」などの背景画の中に登場する風景を、ランドスケープアーキテクトの観点から分析し、実際の里山や庭園の風景写真との比較で、背景画をさまざまな視点で解説しました。
 セミナーのあと、再び展示を見たお客様は「話を聞いてからの絵と聞く前とでは絵の見え方が違う!」と納得。
セミナーのあと、再び展示を見たお客様は「話を聞いてからの絵と聞く前とでは絵の見え方が違う!」と納得。
風景は見る人の教養によってかわるもの・・・なのでーございます。
続いては、間の狂言として、珍元斎が出演。相方の四十一斎と御免奈斎と組んでの「講談:阿波狸合戦」。
 この話は、出品されている「平成狸合戦ぽんぽこ」の元ネタの1つといわれる徳島に伝わるお話で、今回のために書き下ろした珍元斎バージョンを披露。
この話は、出品されている「平成狸合戦ぽんぽこ」の元ネタの1つといわれる徳島に伝わるお話で、今回のために書き下ろした珍元斎バージョンを披露。

背景画の元になった、狸たちが駆け回り、人間と共存していた、かつての日本の暮らしや里山の原風景を口演と寸劇で再現いたしました。
そして、最後は服部保研究員による「照葉樹林と里山」。
「もののけ姫」に登場する照葉樹林から日本の植生の移り変わりや里山の炭文化などを解説。
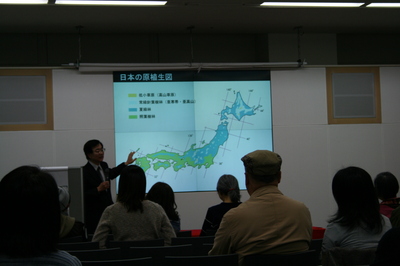 服部先生の撮った屋久島の写真ともののけ姫の背景画の照葉樹林があまりにそっくりでびっくり・・・ほんとの風景から書きおこした絵だということを実証したのでございます。
服部先生の撮った屋久島の写真ともののけ姫の背景画の照葉樹林があまりにそっくりでびっくり・・・ほんとの風景から書きおこした絵だということを実証したのでございます。

この日は満員御礼で、3コマで延べ200人の方々に楽しんでいただきました。
ひとはく背景画セミナー、ああ、見逃したという方のために、あと2回開催します。
いずれも14時から兵庫県立美術館レクチャールームにて下記の日程にて、乞うご期待。
1/9(土) ひとはく背景画セミナー2〜身近な里山とはるかなる琉球〜
「里山の虫:鳴く虫」大谷剛研究員
「里山の虫:ほたる」八木剛研究員
「琉球の自然と風景」太田英利研究員
1/11(祝) ひとはく背景画セミナー3〜里山と植物〜
「背景画の中の植物」高橋晃研究員
「里山講談 クヌギ寅次郎の冒険」河南堂珍元斎
「背景画から読み解く里山の生態系」三橋弘宗研究員
HAT神戸にある県立美術館では
兵庫県と姉妹提携をブラジル・パラナ州の美術館と連携で特別展を開催しています。
特別展の入口のあたりです。
講演中の中瀬副館長です。
ちなみに写っている木は『パラナマツ』でパラナ州の州木です。
マツと思っていたのですが、調べてみるとナンヨウスギ科の高木でよい材木になります。
ブラジル・パラナ州の州都クリチーバは「環境共生都市」として世界的に有名だそうで、
その都市計画と実行の過程、それに関与した日本人、特にナカムラヒトシ氏の話でした。
日本の寺子屋の形式がスラムの教育に導入されたり、日本の知恵も使われたとのことです。
縦割りでなく、建設、教育、交通、ライフライン整備などを総合的に進めて、
ゴミ0化、放置区域の緑地化を環境共生が叫ばれる前に達成して、世界のモデルとなっています。
今回の講演は県立館の連携のひとつとして行われました。
パラナ州の美術館の展示を観ると、中瀬副館長の講演にもあった広大な公園の景観もあり、
クリチーバの風景は地元の誇りであるのだなとの印象を感じることができました。
ブラジル原産のイペの木を使った記念品が抽選で5名の参加者に配られました。
イベはノウゼンカズラ科の高木で、硬く重く丈夫な材になります。
神戸空港のウッドデッキに使われています。
また神戸市中央区鯉川筋にはブラジルとの交流を記念して植樹されています。
別室では、ブラジル音楽のコンサートもあり、美術館はブラジルモードでした。
たまたまですが、演奏者のひとりは中瀬副館長のお友達だそうです。
生涯学習推進室 鈴木 武
戸建て住宅の方々のみならず、マンションなどの集合住宅にお住まいの方々
も、庭や緑を楽しまれてます。庭やベランダには、太陽の直射光も雨もが降りそ
そぎ、風も吹き込みます。そして、そこには多くの植物が植えられています。
庭は多様に「変化する空間」、緑が「生長する空間」なのです。
一方、家には屋根があり、壁があって、外界から守られた私達人間にとって「安
定した空間」といえます。
人間にとって、この「安定した空間」と「変化・生長する空間」が共存するこ
とが重要なのです。このことによって、私達は精神的な楽しみ、安らぎ、ゆとり
などを享受することができるのではないでしょうか。私達の生活の中で、家と庭
の緑、部屋とベランダの緑、この絶妙な関係づくりが庭づくりの極意といえるで
しょう。
住宅の庭のみならず、ベランダでも、家族のライフスタイルにあった縮景の庭、
借景の庭、さらには石の庭までもつくることができます。その際には、庭の方位、
雨・風などの自然現象、周囲の山々や公園や街路樹の緑などの環境、さらには
街並み景観などをよく観察し理解して、それらの良いところを如何に旨く取り込
み、活かすことができるかが重要です。
庭は、私達にとって精神的な楽しみ、安らぎ、ゆとりを与えてくれると共に、
緑の日除けや風除け効果などの気象緩和、野菜や果樹などを通じた食物生産、
生物多様性の維持、さらには街並み景観づくりにまで役立つといっても過言では
ありません。更に、庭はオープンガーデンなどを通じた地域社会づくりにまで貢
献してくれます。
昨今、地球温暖化、化石エネルギー消費、食糧問題などの多くの課題が山積し
ています。私達の庭づくりから、これらの諸課題の解消に向けて挑戦することは、
成熟社会での豊かな生活の質の追求であり、真の庭づくりの意味ではないでしょ
うか。
中瀬 勲(兵庫県立人と自然の博物館 副館長)

写真1 緑の街並み
自分の楽しみのみならず多くの方々と楽しみを共有するオープンガーデンで有名な
北海道恵庭市の街並み景観の一コマ。市民一人一人の楽しみがまち全体を美しくし
ている。恵庭市はわが国でのオープンガーデンの発祥の地の一つである。
本年は「ガーデンアイランド北海道」のテーマのもとで庭づくり、花づくりが全道
で展開されている。

写真2 だんだん畑
阪神・淡路大震災後の震災復興住宅として建設された南芦屋浜の集合住宅の中庭。
住棟間は、だんだん畑として、樹木の植栽のみならず、住民によって野菜なども栽
培されている。住民にとって、見て、手入れして、収穫して楽しめると共に、コミ
ュニティ形成の場となっている。