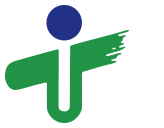ユニバーサル・ミュージアムをめざして18
霊長類学者がユニバーサルな事を考える理由−1
三谷 雅純(みたに まさずみ)
わたしがコンゴ共和国のオザラ国立公園で撮ったゴリラ集団の写真です。前を赤ん坊を背負った2頭のメスと1頭の若いメスが行き、いちばん後ろをオスのシルバーバックが付いて行きます。メスはエサのあるところをよく知っていて、どんどん進みます。シルバーバックは「付いて行っているのではなくて、いちばん後ろで、敵を見張っているのだ」と感想を述べた男性もいました。
わたしが長く取り組んできた学問は「霊長類学(れいちょう・るい・がく)」と言います。「霊長類(れいちょう・るい)」というのは、サルや類人猿や化石人類、それから現生人類を含みます。今、生きているわれわれヒトも霊長類です。
わたしにとって霊長類学は、「今、生きている霊長類の生き方や感じ方をくわしく調べて、ヒトの本質を探る」ものです。ただの「サルの動物学」だと勘違いしている人がいますが、霊長類学は、けっして「サルの動物学」ではありません。ややこしいことに、霊長類学を俗に「サル学」と呼んだりします。実際のところ霊長類学に「サルの動物学」の側面がないわけではないのですが、どちらかと言えば「人類学」という言い方がより正しいと思います。
人と自然の博物館には、化石になったヒトの祖先の展示があります。ですから「人類学」と言えば化石を調べる古人類学(こ・じんるい・がく)を思い浮かべる人が多いでしょう。現に化石を研究している霊長類学者がいます。しかし、霊長類学者には積極的に化石を調べない人も多くいます。なぜかと言うと、霊長類学では、けっして化石になって残ることのない、大昔の(そして今、生きている)霊長類の行動や社会に本質的な興味を感じているからです。我われヒトが持っているはずの「生き方」や「感じ方」、それから「社会の進化」を探っていると言えば、もっとわかりやすいでしょうか。
たとえば、大昔のアウストラロピテクスの女の子の化石が出たとしたら、わたしたち霊長類学者は「この子のコミュニケーションは、どんなふうだったのだろうか」とか、「この子は家族と、どんな関係を持っていたのだろうか」と考えます。「お父さんは、外敵から守ってくれただろうか?」とか、「ひょっとしたら、家族にお父さんはいないのが普通だったかもしれない」とかです。現に(生物としてDNAを受け渡したオスはいたのですが)、社会的には、「お父さん」という存在がいない、つまり「お父さんの可能性のあるオスが多すぎて決められない」霊長類は多いのです。
もう一度書けば、わたしにとって霊長類学は〈ヒトの本質〉を探るための学問です。しかし、現代人は元来のヒトの生き方とは違った生き方をしています。定住をしていますし、都市や農村で生活する人が多くいます。このような生き方が、本当にヒト本来の生き方かと問われれば、ためらってしまうでしょう。どこまでも膨張し続けるインターネットで結ばれる人間関係や、お金の形がどこにもない(しかし、社会的な人の生活には強い影響力を持つ)電子マネーに囲まれた生活というのは、わたしたちの本当の生活なのでしょうか? それを感じてしまう心のすき間に、「狩猟採集こそ、ヒト本来の生き方だった」という思いが忍び込むと、登山や野遊びの好きな人は、思わず、うなずいてしまうでしょう。
前回まで話題にしていた「女性の働き方」は、現代社会が抱える大きな問題です。そして霊長類学から見ると、女性と男性の生き方は現状とはずいぶん違ったものになります。
人と自然の博物館の準備室長(≒初代館長)で霊長類学者の伊谷純一郎さんは、『霊長類の社会構造』(1)という本を、当時、奈良公園のニホンジカを調べていた川村俊蔵さんの調査(2)を基に、(霊長類ではなく)ニホンジカの生活の仕方から、メスとオスは違うのだという話から始めています――わたしが偉い先生に対して「伊谷さん」や「川村さん」と呼ぶ事に疑念を持たれた方がいるかもしれません。霊長類学の研究仲間は、どんなに偉い先生でも「○○さん」と呼ぶ習慣があります。お互いに「○○さん」と呼び合わないと、学生は先生に、後輩は先輩におかしな遠慮が出て、研究者として本当の議論ができなくなるからだと思います。ですから、わたしは敬意を込めて「伊谷さん」「川村さん」「河合さん」と呼んでいるのです。
伊谷さんによれば、メスジカは自分が生まれた土地に長くとどまろうとして、一生を同じ場所で過ごすことが多いそうです。そしてオスジカには放浪ぐせがあり、交尾の季節だけメスジカよりも広い場所をテリトリー(なわばり)として守ります。オスジカのテリトリーはメスジカのテリトリーと重なっているので、メスとオスは自然に出合い、交尾が起こります。交尾が終わったらオスジカは別のメスジカを探し、一方、メスジカはコドモを生んで、自分だけで育てていくのです。これはニホンジカの話ですが、霊長類も、もともとはニホンジカと同じような社会だったと伊谷さんはおっしゃいます。
わたしが鹿児島県の屋久島で調べてみると、ニホンザルの社会(3)でも、自分が生まれた土地に長くとどまるのはメスたちでした。いちばん老齢のメスを、わたしは「母家長(ぼ・かちょう)」と呼んでいました。何頭もいる集団のメスは、皆、母家長の娘や、娘の娘なのだと思います。これに対して、オスは一時的に集団にとどまるだけの存在です。かつては、ニホンザルでよく言われた「ボス」とか「リーダー」という言葉から受けるオスの印象とは、だいぶ違っていました。
もっとも、ヒトの直接の仲間のゴリラやチンパンジー、ボノボのような類人猿では、ようすが変わります。類人猿は、基本的にオスに血縁がある集団を作ります。ニホンザルと違い「父系」なのです。そしてメスは「嫁に行く」ように集団を移動します。このメスが集団の間を移動する行動は、今は化石になったアウストラロピテクスや、ずっとヒトに近いネアンデルタール人でも同じだったと思います。
それよりも、ヒトの直接の仲間――類人猿や化石人類を含めて、ヒトの直接の仲間をホミニッドと呼びます――は、メスとオスで作られる社会が、種によって多様であることの方が重要かもしれません。
たとえば、くわしく調べられたチンパンジーの集団はオスに血縁があり、メスは血縁がないために、オスほど親密ではありません。しかし、チンパンジーによく似たボノボは、別の集団から移ってきたメスたちに血縁はありませんが、親密さはおどろくほど高いのです。さらにゴリラでは、オスにもメスにも血のつながりはないことが多いのですが、集団のメスたちは親密に接します。配偶(はいぐう)の相手を選ぶのは――特に若いオスが相手では――メスなのです。わたしはコンゴ共和国でゴリラを観察しましたが、オスはメスが選んでくれるのを黙って待っていたのでした。
ニホンジカと同じように霊長類でも集団の主役はメスなのだと思います。それが基底音となっては全ての霊長類には流れているようです。ところが、ホミニッドでは「父系」で表される別の要素が加わるようになった。しかし、これまで見たようにホミニッド全体は一種類の社会というわけではありません。チンパンジーのようにオスのつながりが強い社会もあれば、ボノボやゴリラのようにメスのつながりが強い社会もあります。それなら原生のヒトはどうなのでしょうか?
わたしはゴリラの社会に近かった気がします。ヒトも基本的には父系です――社会人類学者のクロード・レヴィ=ストロースがブラジルの先住民ナンビクワラ族の社会を書いた『悲しき熱帯』(4)には、その事がよく示されています――が、女性は血縁はなくても、ゴリラのメスたちと同じように他の女性と仲よく生活することができます。貝であれ、木の実であれ、女性の採集集団は、女性どうしがお喋(しゃべ)りをしながら集めたものでした。
このことに加えて、ホミニッドの中でヒト(あるいは人)をきわ立たせる重要な特徴が、もうひとつあります。それは「(目の前にないものを)イメージする力(ちから)」とか「抽象的な思考能力」(5)です。「抽象的な思考能力」といっても、ここで言っているのは哲学とか数学とかいった難しい事ではなくて、子どもが憶える〈ことば〉とか、子どもの〈絵〉を描く能力の事です――〈ことば〉や〈絵〉は、本質的に抽象的なのです。この能力によって、「ヒト」は生物学的な存在から、社会的な「人」に変化します。
「ヒト」が「人」になるのは、子どもの成長で言えば〈ことば〉を獲得する1歳ぐらいからだと思います。この変化は10歳を超える位まで続きます。〈わたし〉が世界から独立したものだとわかってから、〈あなた〉や〈彼ら〉も、〈わたし〉と同じように〈こころ〉を持つのだということがわかるまで、少しずつ変化するものです。それは「人」として「社会性を身につける」ことに当たります。進化では、〈ことば〉を獲得した時に「生き方」や「感じ方」が一気に組み換えられたのだと思います。その時から、ヒトはチンパンジーやゴリラや、多くの化石人類とは別の生き方を始めたのでしょう。
では、基底音となっては全ての霊長類に流れている(であろう)「メス中心の社会」は、我われの社会に、割合としてどれぐらい残っているのでしょう? それは確かめられるのでしょうか?
確かな事は言えません。しかし、それを確かめてみる努力をしないと、女性が不利な世の中をどのように変えればいいのか、方針も生まれないように思います。少なくとも、今、言える事は、社会を形作るのが男性の専売特許ではないという事です。女性こそが、おだやかに、そして、たゆみなく社会を動かしているのかもしれない。そうであるならば、男性中心に組み立てられた社会では、どこかに矛盾が生まれるのは当然です。その矛盾をできるだけ取りのぞくためには、ユニバーサルなシステムが登場します。皆が等しく役に立つ、それぞれに異なった得意技をみがいて成り立つ社会の登場です。
次回に続きます。
----------------------------------------
(1) わたしが持っているのは、共立出版から生態学講座の1冊として1972に出た古い版です。現在は、『霊長類の社会構造と進化』として新しい版が出ていますが、値段は大変高いので、図書館で買ってもらうといいと思います。
(2)『奈良公園のシカ』(川村俊蔵、1971)
(3) MITANI, M. (1986) PRIMATES, 27: 397-412
(4) クロード・レヴィ=ストロース (2001)『悲しき熱帯』1, 2 [川田順造 訳] 中公クラッシックス.英語であれば無料で公開されています)
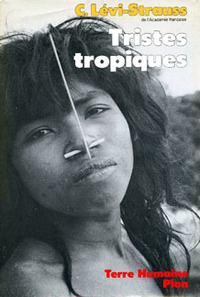 (5) 三谷雅純 (2011) 『ヒトは人のはじまり』(毎日新聞社)
(5) 三谷雅純 (2011) 『ヒトは人のはじまり』(毎日新聞社)

三谷 雅純(みたに まさずみ)
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所
/人と自然の博物館